(本日の連載は下記の
かくして、アンドレスの懸命な説得によってアパサも砦に引き揚げる決断をくだした頃、紆余曲折を経てインカ軍が占拠したその敵砦には、数キロ離れた場所に布陣していたインカ軍本営から、炊事班や衛生班の女性義勇兵たちが、豪雨に打たれながらも、健気(けなげ)な足取りで移動を開始していた。
堅固で巨大なスペイン砦の地下階には、武器弾薬庫や様々な物品収納庫などと並んで大きな食糧庫が備えられている。
その扉の前に、女だてらに連隊長の一人であるマルセラを筆頭に、数名のインカ兵たちや数十名の炊事班の女性たちが、やや興奮気味の面持ちで集まっていた。
今、その食糧庫の扉を大きく開いて、中を覗き込み、その場にいた誰もが「わぁ!!」と歓喜の声を高らかに上げる。
ちょっとした大部屋ほどのスペースを有する広々とした食糧庫の中には、豊かな食糧や飲料がひしめいていたのだ。
乾燥肉や干し魚、乾燥豆、ドライフルーツなどの乾物類はもちろん、生野菜、果物などの生鮮食品、そして、パンや小麦、チーズ、さらには、水、ワイン、ラム酒、ブランデー等の飲料や、砂糖、天然塩、ビネガーなどの調味料に至るまで、その種類も実に豊かで多彩である。
その場にいた誰もがキラキラと瞳を輝かせて、感嘆の吐息を漏らしている。
「さすがにスペイン軍の砦ねぇ!」
「ほんとにそうね!
あるところには、あるものなのね」
頬を紅潮させながら、身を乗り出して言葉を交わし合っている炊事班の女性たちの言葉に、マルセラも深々と頷いた。
それから、彼女は、周りの皆を見渡して、「炊事班のみんなには、ここにあるものを使って、食事を作ってほしいの。隣の部屋には立派な厨房もあるしね」と、明るい声で呼びかけた。

「本当に、ここにあるものを使っちゃっていいんですか?」
興奮と喜びに頬を上気させながら己の方を見つめている女性義勇兵たちに、マルセラは大きく頷いた。
「トゥパク・アマル様が、OKだって。
なんたって、砦で意識不明になったままの大勢のスペイン兵や負傷兵みんなの食事も用意するんだもの。
ただ、貴重な食料には違いないから、大事に使っていきましょう」
「はい!!」
元気に返事をして、女性たちが闊達な足取りで食糧庫の中に入っていく。
食糧庫の中を改めて吟味しながら、溌剌と声をかけ合って献立を話し合っている彼女たちの様子を見守りながら、マルセラの口元も自然にほころんでいく。
こうしていても、もう、この砦の大気中からは殆ど毒素の気配は消えているし、砦の内外が、つい先ほどまで怒涛の戦闘状態であったことなど嘘のように感じられる。
自分の身を振り返っても、今日の昼間までは、この同じ地下階の一隅にある牢獄に捕虜として閉じ込められていたなんて、信じられない思いだった。
インカ軍が砦に攻め寄せてきた時には、その進撃を牽制するための見せしめとして屋上階に連れ出され、味方の軍勢の面前で、アレッチェに酷い暴行を受けたのも、思えば、つい数時間前のことである。
だが、今は、全てが、まるで遥か遠い悪夢であったかのように現実味が無い。
ただ、自分の身体の随所に残る打撲の痣や切り傷の痛みだけが、思い出したくもないあれやこれやの名残を留めているだけだ。
楽しそうに食材を丁寧に切り分けて、いそいそと隣室の厨房へ運んでいく女性たちの姿を見つめながら、気丈に見開かれたマルセラの黒曜石の瞳が微かに揺れる。
(一時的に戦闘状態は収まっているけれど、決して予断を許せる状況ではない。
だけど、もし叶うことならば、この穏やかな時がずっと続いてほしい――)
砦の内外では、負傷兵の救出活動も開始されていた。
幸いにも負傷を免れた健康状態のインカ兵たちは、順番に休息をとって鋭気を養いながら、その逞しい心身に再び気合を入れ直し、豪雨に煙る夜の戦場へ戻っていく。
戦場では、負傷の重症度も様々な兵たちが、血まみれの体を雨に打たれながら累々と横たわっていた。
インカ族の兵はもちろん、そこには無数のスペイン人兵士たちも倒れている。
入り乱れた肉弾戦の中を辛うじて退却していったアラゴン軍の兵たちは、身動きできる自分たち自身が戦場から脱却していくだけで精一杯であったのだろう。
死傷したスペイン兵たちは、その場に置き去りにされるしかなかったのだ。
救出活動を行うインカ兵たちは、トゥパク・アマルの指示のもと、そうした敵方の負傷者も、治療を施すために砦の中へ運び入れた。
さらに、多数の負傷兵たちによって溢れ返っていたのは、アパサ軍やアラゴン軍の熾烈な戦闘が行わた砦下の平原だけではなかった。

アパサやアラゴンたちが死闘を繰り広げた平原のある砦正面側とは反対側の砦の裏手は、断崖絶壁となっており、その崖下には外洋が遥々と広がっている。
その海上では、同日の昼間、ジョンストン提督率いる英国艦隊と砦のアレッチェ軍との間で激しい砲撃戦が行われた。
その海戦においても、アパサ軍やアラゴン軍との決戦によって生じた死傷者数を凌ぐほどの多大な犠牲者が出ていたのである。
この時代、世界の海の覇者と謳われたほど強壮な英国艦隊であったが、いかにそのような英国艦隊といえども、陸の高所に聳(そび)え立つ巨大な砦を相手に戦うのは至難である。
この日の昼間に行われた海戦では、世界最高峰の水準とも言い得る英国艦隊の艦砲射撃でさえも、断崖上の砦から狙い撃つアレッチェの容赦無い要塞砲群の圧倒的威力には抗(あらが)えず、あわや全艦撃沈となるかと思われたほどの惨状であった。
その惨劇を見かねたトゥパク・アマル率いるインカ軍が、砦のアレッチェ軍に戦いを挑み、英国艦隊とスペイン砦軍の戦闘の間に割って入ってきたことによって、英国艦隊は辛うじて全滅を免れた。
しかしながら、あまりに苛烈な海戦によって、英国艦隊の多くの戦艦は海中に没し、攻撃を喰らって海面に投げ出された大勢の英国兵の亡骸や、幸いにもまだ息のある者たちが、砦下の波打ち際や浜辺に次々と打ち上げられていたのである。
トゥパク・アマルの救護の指示は、それらの英国兵たちにも及んだ。
続々と砦に運び込まれてくる負傷兵たちや彼らを搬送してくるインカ兵たちを、一人一人、砦の正門でトゥパク・アマルが迎え入れている。
そんなトゥパク・アマルの傍では、ひどく心配顔の医師が、薬液や包帯を手に握り締め、隙あらば、トゥパク・アマル自身が放置したままの火傷痕や傷口を手当しようと身構えている。
「豪雨の中、皆、誠にご苦労であった」
トゥパク・アマルは吹き込む風雨に己自身も身をさらしながら、ずぶ濡れになって外から戻り来るインカ兵たちを労い、彼らが担架に乗せて運び込んでくる重症のインカ兵やスペイン兵、英国兵たちに痛々しげな視線を馳せる。
「奥の広間に治療場所が設けられている。
従軍医たちも到着しているゆえ、急ぎ、そちらに運んであげなさい」
「はっ!」
救護のインカ兵たちはトゥパク・アマルに深く礼を払って、丁寧に担架を担ぎ上げたまま、俊敏な足取りで奥の間に走り去っていく。
そうしている間にも、血糊や雨土や戦塵にまみれ、もはや人種不明の負傷兵たちが、続々とトゥパク・アマルの迎える砦に到着してくる。
肩を支えられながらであれば何とか自分で歩ける者から、素人目にも相当厳しいと思われる重体な者まで、その負傷の度合いも様々である。
トゥパク・アマルは、傍に控える臣下の者や従軍医たちに向いて再び口を開いた。
「砦内のなるべく導線の良い広間や部屋を治療場所として開放してはいるが、各治療場への収容は、人種ごとに分け隔てるのではなく、重症度によって割り振った方が良かろう。
その方が負傷兵にとっても、搬送してくるインカ兵にとっても、負担が少なく、治療効率も良い」
「畏まりました」
深々と頷いて己の言葉を受け入れ、恭順を示してくれている家臣や周囲の者たちに、トゥパク・アマルも切れ長の目を細めて微笑み、包み込むような眼差しで頷いた。
こうして、運び込まれてくる負傷兵たちは、人種によって分けられるのではなく、負傷の重症度によって、各治療場――砦内の各広間や部屋のことだが――に収容されていく。
怪我の重い者ほど砦正門付近の地上階の治療場に搬送され、早急に治療を受けられるよう配慮された。
その代わりに、負傷度の軽い者たちや自力で身動きできる者たちは、看護兵の手を借りながら、砦の上層階の治療場所まで自ら足を運んでもらうことになった。
担架に乗せられて、あるいは、肩を抱きかかえられて、砦内に運び込まれてくる負傷者のあまりの多さに、救護のインカ兵のみならず、従軍医や看護の女性義勇兵たちも目の回るような、てんてこ舞いの多忙さである。
それでも、インカ兵たちも、そして、医師や看護の者たちも、皆、一丸となって、人種や負傷の軽重の別なく、真心を込めた懸命な対応に勤(いそ)しんでいる。
外見的には黒光りする要塞砲が満載の堅牢な砦ではあったが、今や、その内部は、まるで大病院の中かと見紛うような、外界とは別世界の光景が広がっていた。
砦の正門で負傷兵を受け入れているトゥパク・アマルの視界に、激しい雨の中をこちらに向かってくるアパサやアンドレスの姿が飛び込んできた。
アパサは、叩きつける豪雨でさえも洗い流しきれぬほどに泥土や戦塵、あるいは血糊にまみれ、まるで野性の猪(いのしし)かドブ鼠かと目を見張るような風体と化している。
それでも、遠目から見ても明らかなほど、炯々たる鋭い眼光や全身に漲る猛々しい不敵なオーラは、かつてと変わらず健在である。
いっこうにやむ気配のない雷雨に向かって毒づきながら、大股でこちらに進んでくるアパサの懐かしい姿に、トゥパク・アマルは思わず目を細めた。
アパサとの再会は実に久方ぶりである。
門前でこちらを見守っているトゥパク・アマルに気付いたアンドレスが、小走りで一足早く門の傍まで駆け上がってくると、身を低めて礼を払った。
「トゥパク・アマル様、アパサ殿が同行してくれました」
「ありがとう、アンドレス。
アパサ殿をよくぞ説得してくれた」
感謝の礼を込めて微笑むトゥパク・アマルの元に、まもなくアパサ自身も到着してきた。
アパサの方も、久々の再会を果たしたトゥパク・アマルの無事な様子を目前にして、さすがに常の毒舌も鳴りを潜め、ただ興奮ぎみに鼻腔を膨らませて恍惚と立ち尽くしている。
トゥパク・アマルもまた、深い感慨が突き上げ、大きく瞳を輝かせたまま、言葉を呑んでいる。
「アパサ殿――」
「トゥパク・アマル」
双方共に、戦傷やら、火傷やら、ありとあらゆる汚れやらでボロボロな格好ではあったが、それでも、互いの健在な姿をまるで魂の目に刻み込むかのように、しばし時を忘れて、眼前の盟友を全身の隅々まで見据え合っている。

やがて、トゥパク・アマルが篤い情のこもった声音で言った。
「アパサ殿、よくぞ来てくだされた。
そなたの援軍無くば、今頃、我らはどうなっていたか分からない。
いや、恐らく、砦の内外のインカ軍共に、アレッチェとアラゴンの大軍に一網打尽にされていたことであろう。
誠に、どれほど礼を述べても、述べ尽くせぬ」
一方、そんなトゥパク・アマルの言葉に、アパサは耳元を上気させながらも、ツイッとそっぽを向いて、「礼など…!おまえのやり方はいつも危なっかしくて、放置しておけぬだけだ」と、鼻息を吐いた。
相変わらずのアパサの憎まれ口にさえも、トゥパク・アマルは、懐かしそうにしみじみ聴き入り、微笑んでいる。
対するアパサは、相手の視線から逃れるように、ますます耳を火照らせて周囲に視線を漂わせた。
そうしながら、砦内に続々と運び込まれてくる負傷兵たちの中に、スペイン兵や、さらには英国兵と思しき敵兵たちまでもが混ざっていることに目を留めて、「なぬっ?!」と、大きく喉を鳴らした。
瞬発的に険しく吊り上がった眦(まなじり)で射るようにトゥパク・アマルを睨み、見る間に憤怒に青黒く変わった顔で、アパサが厳しく問い質(ただ)す。
「トゥパク・アマル、なぜ敵の負傷兵どもまで運び込んでいる?
おまえ、まさか、あいつらにまで治療を施して、助けてやろうってんじゃねえだろうな?
そのような敵勢力を補完し続けるようなことをして、この戦いを永遠に続けようってんじゃねぇだろうな?!」
「そなたの言いたいことは分かるし、そなたの意見にも一理ある。
なれど、アパサ殿、そなたも良く知っての通り、この戦いは、植民地支配体制下における圧政を終わらせるためのものであって、スペイン人や英国人など特定の人種を敵と見なしてのものではない。
それにもかかわらず、我らは、あまりにも多くの犠牲を出し過ぎだ。
ましてや、武器をとれぬどころか生死の境を彷徨っている負傷者たちは、たとえスペイン人であろうとも、英国人であろうとも、今や兵士ではなく、一人の傷ついた人間にすぎぬ。
まだ辛うじて灯っている命の火までをも、暴風雨の中に晒したまま、ただ掻き消されるのを看過することなどできようか」
静かな口調ながらも、断固とした意志を秘めて語るトゥパク・アマルの言葉に、しかしながら、アパサは、いよいよ頭髪をメラメラと燃え立たせて、犬歯を獰猛に剥き出した。
「トゥパク・アマル、おまえは、いつまでそのような綺麗事を!!
おまえのその優柔不断な甘さが、これまでどれほどインカ軍をいらぬ危険に晒してきたか、ダラダラと戦さを長引かせ、かえって双方の犠牲者を増幅させてきたか、いい加減に目を覚ましたらどうなのだ!」
いかに同盟者とはいえ、インカ皇帝と目されているトゥパク・アマルに対する一豪族アパサのあまりに歯に衣着せぬ物言いに、周囲のインカ兵たちも、従軍医や看護の者たちも、皆、驚愕して息を呑んでいる。
「アパサ殿、いくらアパサ殿でも、そのような言い方は――」
さすがに堪りかねて、アンドレスが、二人の間に割って入った。
だが、アパサの鋼鉄のような強靭な腕が、アンドレスをドッと突き飛ばした。
「いいか、トゥパク・アマル、この砦に運び込んだ敵兵どもに、今すぐ、一人残らず、止(とど)めを刺せ。
この戦さを一刻も早く終わらせるためにも、そして、ここにいる敵の負傷兵どもと戦って戦場で命を落としたインカ兵たちの魂に報いるためにも、今こそ判断を誤るな」
頭頂から湯気を立てぬばかりに激昂しながらも、アパサの声音はどこか不気味に冷静で、それだけに真に迫った凄みがある。
トゥパク・アマルもまた、アパサの言葉は、ただ感情に流されて吐き出された暴言などではなく、己に対する心底からの進言であると見て取っていた。
それでも、トゥパク・アマルは、静かに首を振り、真摯な、それでいて、有無を言わさぬ強さを宿した口調で決然と言う。
「アパサ殿、そなたの存在は、誠にわたしの右腕そのもの。
そなた無くば、わたしは己の考えに均衡を欠いたまま、偏った道筋へと突き進んで行きかねぬ。
今も、そなたの言葉は、わたしに多大なる気付きを与えてくれている。
とはいえ、そなたの此度の意見は、実行に移すことはできぬ。
まだ命あるスペイン兵や英国兵に敢えて止めを刺すなど、そのようなことは断じてできぬ」
「おまえは、まだ、そのような……!
ならば、俺が、今この場で、手本を見せてやる!!」
ついに本気でブチ切れたアパサの険しい怒声が、砦の高い天井に轟然と響き渡った。

そのままアパサはムズと己の戦斧を握り締め、敵兵なら誰でも構わぬとばかりに、たまたまインカ兵たちによって搬送されてきた一人の負傷兵の方へ突き進んでいく。
鬼のような形相で巨大な斧を構えて迫り来るアパサに、負傷兵を乗せた担架の柄を握っていたインカ兵たちも驚いて目を見張っている。
そんな彼らが運んできた担架の上では、肩から胸にかけて深い刀傷を負ったスペイン兵が、止血の応急処置も虚しく傷口から血を流しながら、苦痛の呻きを必死にかみ殺していた。
これほどの重症を負いながらも意識を失っていない精神力の強靭さに敵ながら感嘆させられるほどであったが、それだけに、当人の苦痛の甚だしさは想像に余りある。
アパサは、その敵負傷兵の担架の前に仁王立ちになると、まるで生贄(いけにえ)を見下ろすが如く冷厳な眼光で相手を睥睨(へいげい)した。
「トゥパク・アマル、誤解をするなよ。
俺は、おまえに反抗する意志など微塵も無い。
ただ、この正念場まで来た以上、おまえに本気で目を覚ましてほしいだけだ。
むしろ、これは、おまえへの捧げ物だと思ってほしい。
おまえがこの戦いに勝利したいと本気で望んでいるならば、これから俺がやってみせるように、敵の負傷兵どもを躊躇なく冥土に送り届けてやることだ。
さすれば、こいつらとて、早く楽になれる。
よく見ておけよ――!」
獲物と定めた眼下の負傷兵から、野獣のごとき鋭い双眸(そうぼう)を一時も離さず、アパサがトゥパク・アマルに向かって大音声を張った。

一方、トゥパク・アマルもまた、鋭利に研ぎ澄まさた切れ長の目を貫くようにアパサに据えたまま、揺るぎない口調で超然と応ずる。
「アパサ殿、抵抗できぬ者を討つなど、そなたは決してしない」
「ならば、おまえのその目で確かめるがいい!!」
アパサのひときわ獰猛な咆哮が、強度に緊張した周囲一帯に響き渡り、と同時に、アパサの筋骨隆々たる腕が大きく戦斧を振り上げた。
己の胴体の真上でギロチンのように生々しい魔光を放つ斧の刃に、担架上の敵負傷兵が、「ヒッ…!」と、声にならぬ悲鳴を上げる。
それが合図であったかのように、戦斧を握り締めたアパサの腕が、猛然と振り下ろされた。
「おやめください!!」
アパサが斧を振り下ろしたのと、その娘が飛び出してきたのと、どちらが早かったのか、周りにいる者たちの動体視力では全く判別できなかった。
いや、一体、何か起きたのか、辺り中の誰もが、すぐには検討もつかなかった。
いずれにしても、気付いた時には、看護の義勇兵と思しきインカ族の若い娘が、風のように群衆の中から飛び出してきて、アパサの斧と敵負傷兵との間に、彼女の身体を挟み込ませていたのだった。

今、敵負傷兵の身体に己の上半身を覆い被せて相手を庇っている娘の頭上1センチほどのところで、アパサの戦斧は、ピタリと、見事なほど完全に止まっている。
その予定されていたが如く完璧な寸止めに、たとえ娘が飛び出して来ずとも、アパサの斧は、負傷兵の体を断ち斬ることはなかったであろうと、トゥパク・アマルの怜悧な瞳は見通していた。
トゥパク・アマルは、目を細めて微笑し、アパサに向かって静謐(せいひつ)な佇(たたず)まいのままに言う。
「アパサ殿、どうかこの場は、その娘に免じて、そなたの刃を納めてはくれまいか」
他方、当のアパサも、さすがに予測外の出来事に両目を瞬かせており、トゥパク・アマルを目尻の端からギロリと睨(ね)めつけて、それから呆れたように深々と鼻息を吐いた。
「おまえの部隊の者たちは、こんな小娘までもが、おまえにすっかり洗脳されているのか」
相変わらずの憎まれ口を叩きながらも、アパサは、己の斧の下で敵兵の上に身を投げ出したまま微動だにせぬ娘の方に視線を馳せている。
「おい、小娘、いつまでそうしているつもりだ?」
「いえ、アパサ殿、彼女は気を失っているんです。
恐らく、本気で負傷兵の身代わりになって、あなたの斧を受けるつもりだったんでしょう。
意識が飛ぶのも無理はありません」
いつの間にそこに来ていたのか、娘の脇に跪(ひざま)ずいたアンドレスが、顔面蒼白になって、憤怒を滲ませた険しい目で、キッ、とアパサを見上げた。
そうしながら、アンドレスは、うつ伏せたまま失神している娘の細い肩を懸命に揺すって、「しっかりしろ、コイユール、コイユール…!」と、必死に呼びかけている。
「気を失っているだぁ?
俺は、その小娘には、何もしてねぇぞ。
そもそも、勝手に飛び出してきたのは、その女の方じゃねえか。
それで気絶したからって、俺のせいだなんて言われちゃ堪らねぇぜ」
いつになく己に厳しい眼を向けてくるアンドレスに少々たじろぎながらも、アパサが、憮然として言い放つ。
「アパサ殿、いくら覚悟の上で飛び出してきたからって、本当に頭上から斧が降ってくれば、普通の感覚の女性なら、気のひとつやふたつ失って当然でしょう」
憤りを隠せぬ声音で言い返すと、アンドレスは、意識を失っているコイユールの華奢な身体を横抱きに抱き上げ、アパサの眼前に決然と立った。
直近で立たれると、今ではトゥパク・アマルに追いつかぬばかりに長身のアンドレスが、中肉中背のアパサを見下ろすかたちになっている。
「アパサ殿――」
「な、なんだ、アンドレス、おまえの大恩ある師匠様のこの俺に、何か文句でもあるってぇのか?
もしや、その小娘は、おまえの知り合いか?
いや、まさか…おまえの女だったりとか?」
「――…!」
皮肉を込めた冗談で言ったつもりの己の言葉に、アンドレスがあまりに大きく反応したため、アパサも、刹那、目をまん丸くしていたが、すぐにも、「え〜?!マジでっっ?!」と、素っ頓狂な声を上げた。
「ま、さ、か、ほんとに、おまえの女なのか?
あのヒヨッコだったおまえの?!
ブワッツハハハ――!!
こりゃあ、とんだ余興じゃねえかっ!」
これでもかと毒々しい言葉を浴びせながら豪快な笑い声を上げているアパサの面前で、アンドレスは、瞬間、耳まで真っ赤になる。
が、その次の瞬間には、即座に青黒い顔色に変わって、いよいよ険しく両目を吊り上げた。
「何が可笑しいんです?!
第一、そのような下品な言い方はやめてください……!
それより、アパサ殿、後生ですから、どうかその物騒な斧をお納めください!」

アンドレスは、今も気を失っているコイユールを抱き上げている両の腕に力を込め、己を奮い立たせるようにして語を継いでいく。
「インカ軍、ひいてはインカの民全体のことを真に思ってのアパサ殿のお考えは、トゥパク・アマル様も仰る通り、僭越ながら、俺も誠に有難く、そして、実際、一理あると感じております。
ですが、この砦にいる敵方の負傷兵たちを本当に手に掛けるようなことをしたら――、ひどく傷ついて無抵抗な彼らを本当に殺(あや)めるようなことをしたら、スペイン側や英国側の憎しみはどれほど膨れ上がることでしょうか。
そうなれば、敵方に囚われ捕虜となっているインカ軍の兵たちは、即座に、皆殺しにされてしまうことでしょう」
「――ふん、そんなことは分かり切っている。
それも覚悟の上で、いかなる状況であろうが、一兵でも多くの敵兵力を減ずる断固とした意志と実行力が無ければ、勝利などできぬ。
それを身をもって教えてやろうと思っただけだ」
「アパサ殿……!」
アンドレスは、眉根を強く寄せた苦悩の面持ちで、今も意識を失くしたままの腕の中のコイユールの方に視線を落とした。
そんな彼をまじまじと眺め渡してから、「くそッたれ…!」と、口汚く吐き捨てた後、ついにアパサは、ゆっくり斧を石床に下ろした。
その瞬間、張り詰めていた辺りの空気が、ふっと、緩む。
「せっかく手本を示してやろうと思ったが、小娘まで飛び出してくる始末。
トゥパク・アマルにも、おまえにも、この砦中の誰にも彼にも、まったく、すっかり、興ざめだっ」
嫌味の連打に弄(なぶ)られながらも、アンドレスは、深く安堵の息をついた。
と、そのアンドレスの嘆息に重なるように、グーーッ、と、アパサのお腹が大きく鳴った。
「……!」
顔を赤らめて気まずそうに言葉を呑んだアパサの傍に、トゥパク・アマルが歩み寄り、ニッコリ笑って言う。
「アパサ殿、奥に晩餐の用意が整っています。
このような場所ゆえ、豪華な饗宴とはいかないが、そなたの大いなる働きに報いんと、皆が真心込めて作ってくれた食事です。
それに、そなたとは色々と積もる話もある。
さあ、アパサ殿、わたしと共に晩餐の間へお越しください」
軽くアパサの肩に触れたトゥパク・アマルの手に促されて、砦の奥に向かって踵を返したアパサの後ろ姿に、アンドレスは身を低めて、心底から礼を払った。
「アパサ殿、武器を納めてくださり、本当にありがとうございます」
「フン、今はやめた、というだけにすぎん。
俺がこの砦にいる間、その気になれば、いつでも、敵の負傷兵どもをあの世に送ってやる心積もりがあることを忘れるな」
振り向きもせず答えたアパサの筋肉質な背に向かって、アンドレスは、今一度、深々と頭を垂れた。
アパサの方に下げていた頭を上げて、アンドレスが、腕の中に抱き上げているコイユールに視線を向けた時、ちょうどコイユールも意識を取り戻したところであった。
彼女は艶やかな長いおさげを揺らして微かに首を振ると、ゆっくり目を開き、まだ朦朧とした意識の中で辺りに視線を漂わせている。
「コイユール、良かった!
意識が戻ったんだね」
歓喜の表情で夢中で己を見下ろしているのがアンドレスだと気付くと、コイユールは、激しい驚きの顔で、「えっ?」と、大きく息を詰めた。
くっきりした彼女の目元が、弾かれたように見開かれていく。
「アンドレス、どうし…て……?」
意識が回復したばかりで、まだ上手く状況が呑み込めぬ様子のコイユールではあったが、ほどなく、「そうだわ、アパサ様は?それに、負傷したスペイン兵の人は?」と切迫した声を上げた。
「大丈夫だよ、コイユール。
アパサ殿は武器を納めてくれたし、君が庇った負傷兵も治療場に運ばれていった」
優しい眼差しで微笑みながら答えるアンドレスの澄んだ瞳を見上げながら、コイユールは言葉に尽くせぬ安堵の表情で、「そう…良かったわ。本当に良かったわ」と、涙声を漏らした。

それから、揺れる黒曜石の瞳でアンドレスの顔を真っ直ぐ見つめると、深い感動を帯びた声音で囁くように言う。
「アンドレス、あなたが無事で本当に良かった。
またこうして、あなたに会えて……」
「コイユール――俺もどんなに君に」
堪え切れぬ愛しさから、コイユールを抱き上げているアンドレスの腕には、無意識に力がこもっていく。
と、その時、何者かの手が、ポンッ、と、アンドレスの肩を叩いた。
「なんだよ、今、とても大事なところなのに」
そう言って半顔だけ振り向いたアンドレスの後ろには、己の肩に手を置いたロレンソの姿がある。
「あー、邪魔をして悪いのだが、アンドレス、そなたたち、とりあえず今はそれぐらいにしてはどうだ?」
コホンッ、と軽く咳払いしつつ、そう窘(たしな)めたロレンソは、視線で周りをグルリと示した。
「えっ?――ギョッ!!」
アンドレスとコイユールが周囲に目を転じれば、その辺りに集まっていたインカ兵や看護の義勇兵たちの完全に注目の的となっている。
咄嗟に我に返った二人の顔から、同時に真っ赤な火が噴き出した。
コイユールは瞬時に相手の腕の中から飛び降りると、頬を紅潮させたまま、懸命に瞳で訴える。
(アンドレス、早く任務に戻って)
(わ、分かった……また後で!)

顔から炎を上げたまま急いでアンドレスがその場を立ち去る間にも、コイユールは、たちまち看護班の年上の女性たちから取り囲まれた。
「ふ〜ん、前から、あんたとアンドレス様は、なんだかアヤシイと感じてたのよ。
でも、まさか、あたしたちと同じ貧しい農民出の娘のあんたと、皇帝陛下の甥のアンドレス様とじゃ身分が違いすぎると思ってたの。
だけど、さっきの様子だと、あんたたちやっぱり!
さ、今日こそは白状なさいな」
「い、いえ、たまたまアンドレス様のお屋敷があったのと同じ村の出身で…ちょっとした事情があって、子どもの頃からの知り合いで……そ、その……」
年上の女性たちから強く迫られてアタフタと答えるコイユールに、女性たちは「ウフフ」と笑って、コイユールの滑らかな額を可笑しそうに小突いた。
「まあ、そんなに恐縮しなくていいのよ。
アンドレス様は、あたしたちから見れば、どうしたって子どもなの。
まだまだあまりに若すぎるから。
男としては、やっぱり、トゥパク・アマル様の方よねぇ!」
開けっ広げな調子で朗らかに語らいながら、「そうそう」と意気投合している女性たちに、コイユールは目を瞬かせながら「でも、トゥパク・アマル様には、ミカエラ様も皇子様たちもいらして…」と固唾を呑んでいる。
「まぁ、ふふふ、ほんと、あんたって初心(うぶ)な子ねぇ!
そういうこととは、また別なのよ。
ま、いいわ、早く治療場に戻らなきゃならないから、今日のところはこれくらいにしておいてあげる」
そう言って高らかに笑いながら踵を返した年上女性たちの後ろ姿を見送ると、コイユールは、同年代の少女たちにも目をやった。
「あの…」
「あ、いいの、いいの、わたしたちにも遠慮しなくていいのよ。
わたしたちも、どっちかというとトゥパク・アマル様が、ね――やっぱり、ずいぶん大人だし♪」
「はぁ……」
返す言葉を失って、さらに目を瞬かせているコイユールの腕を取って、少女たちも治療場の方に闊達な足取りで歩き出す。
「それより、コイユール、さっきはすごく心配したのよ。
アパサ様が斧を振り上げているのに、いくらなんでも危なすぎるわよ」
賑やかに言葉を交わしながら、コイユールを伴って、若い娘たちも治療場の方へ去っていく。
そんな彼女たちのやり取りを物陰でそっと聞いてしまったロレンソは――というのも、アンドレスとの間柄を悟られたコイユールが、女性陣に詰問されて辛い目に合わされるのでは、と案じて、密かに見守っていたのだが。
そんな自分の懸念が取り越し苦労であったことに安堵しつつも、さすがに複雑な心境を禁じ得ず、息を呑んでいた。
(彼女たちの今の会話は、アンドレスには黙っておこう…。
しかし、アンドレス、そなた、もっとしっかりしないといかんようだなぁ)
トゥパク・アマルに導かれて、ほどなくアパサは晩餐の間に続く重厚なドアの前に立っていた。
ドアノブに手をかけて扉を開きながら、「さあ、中へ」と、トゥパク・アマルが微笑みながらアパサを促す。
そんなトゥパク・アマルを改めて直近で眺めやりながら、アパサは、今さらながら、トゥパク・アマルの肌を覆う酷い火傷痕や投打痕に気付いて、眉をひそめた。
「トゥパク・アマル、その火傷や怪我はどうした?
その傷――足蹴(あしげ)にでもされない限り、普通に殴られた程度では、そんなふうにはならないぞ。
一体、何があったのだ?」
「応急処置も済んでおり、案ずるには及びませぬ。
そなたこそ、戦場で受けた大傷だらけで、全身たいそうな状態ではないか」
「フンッ、これしきのカスリ傷、唾でもつけときゃ勝手に治る」
そう言って鼻息を吐き出したアパサを扉の内部に導き入れて、トゥパク・アマルが、さらに広間の内部へ歩み進んでいく。
部屋中に立ち込めた料理の芳しい匂いや漂いくる温かな湯気に誘われるように食卓の方に目をやったアパサの顔が、パァッ、と大きく輝いた。
広間の中央には幾つもの燭台で照らし出されたテーブルが置かれており、その上には、女性義勇兵たちが真心込めて用意してくれた料理の数々が並んでいたのだ。

紅色唐辛子を利かせたライム風味の魚介マリネ、燻製肉やカナッペ、パン類、魚介類やチューニョ(乾燥ジャガイモ)をトマトで煮込んだブイヤベ−ス風ス−プ、茹でたての大粒トウモロコシ、黄色唐辛子を添えた魚介のフライ、冷製ポテトのクリームチーズ風ソースの和えもの、茹でたジャガイモや葉物野菜にレモンと紫タマネギを添えたサラダ、スパイスで味付けされた黄金色に輝くライスなど――。
海辺にある砦の地の利を生かした海産物をメインに、砦の食糧庫に保存されていた食材を合わせて作られた、素朴ながらも丹精込めたインカの伝統料理の数々である。
「こいつはウマそうじゃねぇか、ありがてぇ」
ホクホク顔でそう言って手近な椅子に腰を据えると、早速、料理に手を伸ばしているアパサに、「心ゆくまで召し上がってください」と、トゥパク・アマルが目を細めている。
まだ湯気の立ちのぼるトウモロコシから黄金の粒をむしって口にほうりこみ、甘美な旨味を噛み締めながら、アパサがしみじみと言う。
「これでチチャ酒でもあれば最高なのだがなぁ」
「わたしも同じ思いだが、いつ敵襲があるか分からぬ状況ゆえ」
そう苦笑するトゥパク・アマルに、「そんなこたぁ、言われなくても分かってる」と、アパサが片眉を吊り上げた。
「アパサ様、どうぞこちらも召し上がってください」
不意に、耳元で聞き慣れない若い女性の声が響いて、アパサは、ハッ、と顔を上げた。
晩餐の間で、トゥパク・アマルやアパサのために食事の給仕をしていた数名の女性義勇兵たちの中にいたマルセラが、大きな土鍋から取り分けた熱々のスープ皿を、トゥパク・アマルとアパサの前に笑顔で差し出していたのだ。

スラリと長く伸びた健康的な褐色の手足に、青年のような凛々しさと女性的な魅力を兼ね備えた中性的な風貌のマルセラ――突然の彼女の出現に、料理を掻き込んでいたアパサの手が、ピタッ、と止まる。
本来は酒豪のアパサも、今は一滴も飲んでいないはずであったが、固まったまま耳元を上気させている。
そんな中、「そういえば」と、思い出したようにトゥパク・アマルが二人を見交わした。
「アパサ殿とマルセラは初対面であったな。
アパサ殿、こちらはビルカパサの姪御殿のマルセラです」
トゥパク・アマルの紹介に、マルセラも、「アパサ様、お初にお目にかかれて嬉しく思います。アパサ様の武勇伝は、叔父から多々聞き及んでおります」と、深い敬意を宿した声音で、闊達に言い添える。
「あっ、あの堅物で無骨なビルカパサの野郎に、…い、いや、ビルカパサ殿に、あなたのような姪御殿がいらしたとは、やっ、全く驚きです」
照れて急に言葉遣いの変わったアパサがどこか微笑ましくて、スープの匙を口に運びながら、トゥパク・アマルも思わず相好(そうごう)を崩した。
「『堅物で無骨な野郎』とは、このわたしのことですかな?」
「――!」
いきなり背後で聞き覚えのある野太い男の声が響き、アパサは、口いっぱいにほおばっていた大量のトウモロコシの粒を、思わず丸ごと呑み込んだ。
と、同時に、激しく咳き込む。
「アパサ様、しっかり!」
ゲホゲホむせているアパサの方に急いで冷水を渡しながら、マルセラが、ハッと、目を上げて、「あ、叔父様!」と明るい声を上げた。
アパサが喉に詰まらせたトウモロコシを水で流し込んでいる間にも、彼の背後から現われたビルカパサに目を留めたトゥパク・アマルが、眦(まなじり)に力を宿して、スッと、立ち上がった。
ビルカパサもまた、トゥパク・アマルの傍に力強い足取りで歩み寄り、身を低めて深々と恭順を示す。
「トゥパク・アマル様、只今、戻りましてございます」
「ビルカパサ、よくぞ戻った。
先刻は、あれほどの苛烈な砲撃を浴びながら、よくぞ皆を護り、命長らえさせてくれた」
篤い情のこもった声音で言うトゥパク・アマルの前で、ビルカパサも、多大な安堵を隠せぬ感極まった声で答える。
「混戦状態にあったインカ軍本隊を安全に引き上げるため、少々時間を要し、戻り来るのが遅くなってしまいました。
戦さの最中、陛下のおられるはずの砦の気配が消え去った時には、どれほど案じたことか。
陛下がご無事で本当に良かった」

まさしく、たった今、戦場から馳せ戻ったばかりのビルカパサは、この晩餐の間に入室するために急いで戦塵だけは払い落していたものの、此度の戦闘で最も激しい砲火に身をさらしていた彼の全身の傷跡は、いかにも生々しい。
「ビルカパサ、そなたには誠に心配をかけた。
あの時、この砦の中でも、いろいろあってな。
それより、そなたは、すぐに傷の手当てを受けねばならぬ」
「いえ、トゥパク・アマル様、こんなものは何ほどでもありません」
そう逞しい笑顔で応じて、ビルカパサは、鷲鼻の際立つ凛々しい横顔を、今度はアパサの方に振り向け、深く礼を払った。
「アパサ殿、思いもかけぬ此度の援軍、誠に有難く――!」
「おう」
短く答えたアパサもまた、さすがに感無量の面持ちである。
トゥパク・アマル、アパサ、ビルカパサ――最重装備を擁した敵軍の猛攻によって多大な犠牲を強いられながらも、一兵でも多くの命を守らんとして我武者羅な攻防戦を繰り広げ、こうして奇跡にも思える再会を果たした三人。
その胸中に去来するものはあまりに大きく、今は言葉も無く、ただ熱く互いを見交わすばかりであった。
こうしてビルカパサも晩餐の座に加わり、三人で食卓を囲みながら、改めてトゥパク・アマルとビルカパサの視線がアパサに注がれる。
「それにしても、アパサ殿、そなたが援軍として当地に現れてくれたことは誠に有難いことなのだが、しかし、そなたにはラ・プラタ副王領(現在のボリビア周辺)の守備を任せていたはずではなかったかと」
そう穏やかな口調で問うトゥパク・アマルに、アパサは唐辛子を塗りつけたジャガイモを口に押し込みながら答えた。
「俺は、おまえの指図を受ける気はないと伝えたはずだ。
もちろん、俺の留守中は、信頼できる部下に後を預けてある。
それに、あそこは、今、敵兵力が手薄になっていて、俺がいるまでもないのだ。
ラ・プラタ副王領で敵軍を総(す)べていた敵将フロレスも、あそから引き揚げちまったしな」
「アンドレスたちが収集した情報によれば、フロレス殿は、ラ・プラタ副王領から当地に呼び戻され、此度の海戦では、スペイン軍の艦船に指揮官として乗艦していたとか。
昨日の英国艦隊とスペイン艦隊の海戦は凄まじく、両海軍に多くの犠牲者が出たようだ。
フロレス殿の身も案じられる」
敵将の一人でありながらも相手の身を慮(おもんばか)って眉根を深く寄せて言うトゥパク・アマルに、アパサもチラリと視線を馳せた。
「トゥパク・アマル、おまえ、あのフロレスに会ったことがあるか?」
「いや」と、トゥパク・アマルは静かに首を振って、語を継いだ。
「だが、ラ・プラタ副王領への遠征中にフロレス殿と面識のあったアンドレスから、フロレス殿の人となりは良く聞かされている。
アンドレスによれば、スペイン軍の高官にしては珍しく公明正大で、偏見の少ない人物だとか」
アパサは「うむ」と頷きながら、スープの残りをうまそうに喉に流し込んだ。
「あいつは白人だが、このペルー生まれだから、スペイン渡来の生粋のスペイン人たちから、ずいぶん差別や偏見を受けてきたらしい。
だから、人権の欠片もなく搾取され侮蔑されてきたインカ族の苦労が、あいつには少しは分かるのかもしれんな」
「そなたも、アンドレスも、同じようなことを言う。
そのような人物ならば、わたしもフロレス殿に直に会って、是非とも話をしてみたいものだ」
美しい輪郭を燭台の灯りに照らし出しながら、物思わし気に語るトゥパク・アマルに、ビルカパサが身を低めて呻くように言う。
「トゥパク・アマル様、わたしも同じ思いです。
が、――昨日の海戦で、火達磨になったスペイン艦をフロレス殿が指揮して、英国艦に突っ込んでいくのを見かけたとの海上偵察隊の報告がございます」

「叔父様の申し上げた通りです。
この砦に囚われる前、わたしは海上偵察に出ておりましたので、遠目からではありますが、そのような様子を確かにこの目で見ました」
不意にマルセラの声が食卓の傍で響き、皆が一斉に息を詰める。
「なんと火達磨になった自艦を操縦して、自身もろとも敵艦に――」
晩餐の間に、重々しい空気が垂れ込めた。
やがて沈黙を破って、アパサが再び口を開いた。
「それで、昨日のスペイン艦隊と英国艦隊の決戦は、結局、どちらが勝ったのだ?
おい、トゥパク・アマル、聞いてんのか?」
深く思い拭けった眼差しで燭台の炎を見つめているトゥパク・アマルに代わって、ビルカパサがアパサに向いて答えた。
「アパサ殿、わたしがお答えしましょう。
昨日の海戦では、最新鋭の戦艦を擁する英国艦隊が圧勝し、拿捕(だほ)されたスペイン艦の海兵たちは英国艦の捕虜として大勢囚われました。
そして、一夜明けて、次は上陸作戦に向けて、このスペイン砦を制覇しようと意気揚々と外洋から戻り来た英国艦隊でしたが――。
しかし、英国艦隊の思惑に反して、この堅牢なスペイン砦は英国艦隊の艦砲射撃をものともせず、逆に、砦の要塞砲による猛攻で英国艦隊を圧倒してしまったのです。
我らインカ軍が間に入って参戦してこなければ、恐らく、英国艦隊は、砦の要塞砲によって、全艦撃沈の憂き目を見ていたことでありましょう」

ビルカパサの言葉に聴き入りながら、アパサが強く眉間に皺を寄せた。
「それでは、この砦のスペイン兵どもは、英国艦に囚われて捕虜とされていた自分たちの仲間にまで、容赦なく砲火を浴びせたってことか?
ひでぇ話だな…。
だが、それぐらい冷徹に戦ったからこそ、スペイン砦は優位に立てたのだろうがな」
そう嘯(うそぶ)きながら鋭利な視線をトゥパク・アマルに馳せたアパサを、トゥパク・アマルは黙って受け流し、冷水を満たしたグラスに口をつけた。
そんな二人の様子を見交わしながら、ビルカパサが軽く咳払いをして、またアパサの方に向き直る。
「ところで、アパサ殿。
アパサ殿に守護をお願いしているラ・プラタ副王領のことですが、かの地は、アパサ殿やアンドレス様の遠征が功を奏し、ここまでインカ軍が勢力を伸ばしてこられたわけですが、敵軍としては、機会さえあれば、いつでも奪還したいと考えているはずです。
あまり長くアパサ殿が現地を不在にするというのは……」
厳格な面持ちで語るビルカパサに、アパサは、チッ、と忌々しげに舌を鳴らし、相手の視線を払い除けるようにして顔の前で手を振った。
「全く煩(うるさ)いやつだな。
そんなことは、おまえに言われずとも分かっている。
あっちは出来る部下にしっかり任せてあるから、余計な心配は無用だ。
それより、おまえもトゥパク・アマルも、このような敵砦に勝手に無謀な戦いを仕掛けおって。
斥候たちからその噂を聞き付けて、居ても立っても居られぬ心境だった俺の気持ちも察してほしいものだぜ。
案の定、俺が飛んでこなければ、おまえたちは今頃どうなっていたか分からんぞ」
「そのことにつきましては、わたしとて、アパサ殿にどれほど恩に着ていることか…」
今度はビルカパサとアパサの間に張り詰めた空気が流れ出した時、ちょうどタイミングを見計らったかのように広間の扉が元気に開け放たれて、アンドレスとロレンソが若々しい笑顔を覗かせた。
「すいません、遅くなってしまいました。
負傷兵たちの搬送もだいぶ秩序立ってきましたので、やっと、こちらに来られました」
「他の搬送の兵たちにも、順次、休息をとれるようローテーションも組めましたので、どうかご安心ください」
トゥパク・アマルは、若者二人を優美な仕草で食卓の方へ手招きする。
「アンドレス、ロレンソ、誠にご苦労であった。
さあ、そなたたちも、こちらに来て食事を摂りなさい。
ずいぶん空腹であろう」
「ありがとうございます!」
長時間に渡って生死を賭けた作戦遂行に挑んでいた間も、その後の対応に追われていた間も、無我夢中で空腹のことなど忘れていたが、今、美味しそうに並べられた料理を前にして、アンドレスもロレンソも、自分たちが死ぬほど腹ペコだったことを痛感していた。
二人とも食卓ごと抱え込んで一気に胃袋に流し込んでしまいたいほどの激しい食欲を覚えていたが、それでも、ロレンソは、トゥパク・アマルの隣に座しているアパサに気付いて、深く真摯な礼を払った。
その様子に目を留めたトゥパク・アマルが、「そういえば、ロレンソ、そなたもアパサ殿とは初対面であったな」と微笑んで、二人をそれぞれに紹介する。
「アパサ殿、こちらはアンドレスの学生時代からの朋友で、反乱幕明け初期よりインカ軍に参戦し、今では、わたしの重側近の一人でもある連隊長のロレンソです。
ロレンソ、こちらは、そなたもよく知っての通り、わたしの一番の同盟者であるラ・プラタ副王領の豪族アパサ殿だ」
トゥパク・アマルの言葉に、今一度、ロレンソはアパサに丁寧な礼を深々と払った。
「アパサ様、お初にお目にかかれて誠に光栄です」

アンドレスと同年齢にしては、ぐっと大人びた風貌と、涼やかで怜悧な眼差しを宿したロレンソをひとしきり眺めやったあと、アパサは、アンドレスにも目を向けて、口を開いた。
「アンドレスと同い年には見えねえなあ。
ロレンソ、おまえ、ガキの頃からの付き合いじゃ、アンドレスの尻拭いに、ずいぶん色々と苦労させられてきたんじゃないのか?
まぁ、それに懲りず、今後ともアンドレスのことを宜しく頼む」
急に自分の保護者然とした口ぶりになっているアパサの言葉に――しかも、指摘が図星であっただけに…、アンドレスは口に詰め込んでいたフライを吹き出しそうになった。
一方、そんなアンドレスをよそに、ロレンソは、「いえ、滅相もありません。アンドレス様に助けられているのは、いつもわたしの方なのです」と、沈着な、それでいて若者らしい笑顔で明るく応じている。
そのようなやり取りをトゥパク・アマルやビルカパサも穏やかな表情で見守っており、若い二人が座に加わって、晩餐の間に、再び和やかな空気が流れ出したようだった。
やがて、ひとしきり料理を胃袋の中におさめたアンドレスが、思い出したように顔を上げた。
彼は、トゥパク・アマルの方へ居住まいを正して向き直ると、真面目な顔つきで口を開く。
「トゥパク・アマル様、先ほど負傷兵の治療場を巡回してきたのですが、負傷兵たちは重症度に応じて各治療場に運ばれて、緊急性に応じて治療を受けておりました。
インカ軍の者だけを優遇するのではなく、そして、スペイン兵や英国兵を捕虜扱いしないというトゥパク・アマル様のご意志はよく分かりました。
ただ、激しく敵対していた者たちを同一空間にいさせるというのは、双方の負傷兵たちの気が休まらぬ恐れもありますし、トラブルの元になりそうな心配もございます」
言葉を選びながらも率直な意見を述べるアンドレスの言葉に黙って耳を傾けながら、トゥパク・アマルも「うむ、それで?」と先を促す。
「敢えて人種を分け隔てせず、共に過ごすことで敵対心を軽減し、むしろ連帯感を高められるかもしれないという陛下のお考えは俺にも察せられるのですが、なにぶん先刻まで生死を賭けて戦い合っていた者同士です。
良い方にいけばいいのですが、逆に、負傷兵たちの間で争いの火種が生まれ、殺傷沙汰に至る危険さえあるのではないかと…。
怪我で身動きもできず気力も弱まっている現在はまだしも、回復して兵士としての体力や鋭気を取り戻した時が特に心配です」
「なるほど、そなたの言う事には一理ある。
それでは、どうしたら良いと思う?」
トゥパク・アマルは、切れ長の美しい目元に真摯な光を宿して、静かに問う。
それに対して、アンドレスもまた、澄んだ琥珀色の瞳を思慮深くさせて、頭に浮かんでくる考えを噛み締めるように言葉に変えていく。
「負傷兵たちは人種混合で重症度ごとに各治療場に搬送され、既に治療も開始されておりますので、これから改めて人種ごとに再配置するのは難しいでしょう…。
ですので、現状のまま、負傷兵たちの間で衝突や緊張関係が生まれぬよう、我々の方でいっそう気を付けて監視していく必要があると思います。
特に、命に関わるようなトラブルは最も避けねばらぬことですので、治療場へは、武器の持ち込みを一切禁止してはいかがでしょうか」
再び「なるほど」と応じた後、トゥパク・アマルは、アンドレスの発言を吟味するように一呼吸おいてから、ゆっくり頷いた。
「分かった。
アンドレス、そなたの進言に従おう。
治療場に出入りする者は全て、一時的に武器を預かるということにいたそう。
なお、武器の持ち込みの制限は、スペイン兵や英国兵のみならず、インカ兵にも等しく適用する」
トゥパク・アマルの言葉に、アンドレスやビルカパサ、ロレンソが共に、「はっ」と恭順を示した。
その脇で、そもそも敵兵を治療すること自体に不満いっぱいのアパサは、口を「への字」に曲げながら、きつく腕組みをして、ムスッと椅子にふんぞり返っている。
そんなアパサも含め、その場の全員に穏やかな目を配りながら、トゥパク・アマルが温かな微笑を湛(たた)えながら言う。
「わたしは、インカ族の者たちも、スペイン人も、英国人も、互いの違いや怨恨の壁を乗り越え、心をひとつに合わせることができる日がくると信じている。
確かに、容易なことではないかもしれぬ。
なれど、そなたたちも、そのような気持ちで、砦の兵たちはもとより、国中の全ての者たちを見守ってほしいのだ」

同じ頃、治療場の看護の女性たちも、順番に食事休憩をとっていた。
コイユールもまた、自分の番がくると、負傷兵たちの血で染まった手を清水で洗い流し、食堂として用意された大広間へと向かう。
その広間で調理班の女性たちから料理を受け取り、同僚の看護の少女たちとテーブルを囲みながら、コイユールは思わず感嘆の吐息をついた。
「まあ、なんて美味しそう」
湯気の立ち昇る具だくさんのスープや魚介料理、茹で野菜、柔らかなパンなどを眩しそうに見つめて、周囲の少女たちも、うんうん、と興奮気味に頷いている。
「こんなにちゃんとしたお料理を頂くのは久しぶりね」
「いただきまあす!」
嬉しそうに料理を味わっている仲間たちと一緒に、コイユールも温かなスープを口に運ぶ。
そうしながら、食堂の大広間全体をゆっくり眺めてみる。
砦内のスペイン兵や英国兵は、皆、何らかの負傷や体調不良の者たちで、そのため彼らは治療場の方にいるので、食堂内にいるのは健康なインカ兵たちばかりであった。
その広間にいるインカ兵たちは4〜50名といったところだが、彼らも、順次、ローテーションで休息をとっているのだろう。
インカ兵たちもまた、料理に舌鼓を打ちながら、和やかに談笑したり、一人でいる者も自由にゆったり寛いでいる。
そんな平穏な光景を眺めているうち、コイユールの心には、先ほど再会を果たしたアンドレスの面影が優しく甦ってくる。
(アンドレス、戦場から戻ってからも、すごく忙しそうだったけれど、ちゃんとお食事できたかしら。
それにしても、あんなに激しい戦いだったのに、アンドレスも、マルセラも、トゥパク・アマル様も、ロレンソ様も、皆、無事でいてくれたなんて、本当に夢みたいだわ)
泉のように湧き上がりくる喜びを胸いっぱいに感じながら、コイユールは、神に全身全霊で感謝の祈りを捧げずにはいられない。
と、その時、不意に、背後から、馴染みの従軍医の少々緊張した声が響いた。
「コイユール、ここに居たのか。
良かった、ちょうど探していたのだ」
「先生、どうされましたか?
急変した負傷兵の方がいるのですか?
すぐに戻りましょうか」
我に返ったコイユールが老医師を振り向いて、心配そうに問う。
医師は、「いや、急変というわけではないのだが――」と、やや言葉を濁し、低い声で語を継いだ。
「コイユール、手を借りたいことがある。
食事を済ませてからでよいので、後で、わたしのところに来ておくれ」
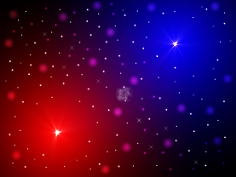
コイユールが急いで食事を終えて治療場に戻ると、彼女に気付いた先ほどの従軍医が治療の手を止めて、(こちらに…)と、視線で合図を送ってきた。
コイユールも頷き、足早に治療場を出て行く従軍医の後を、慌てて追いかける。
このインカ族の従軍医は、高齢ながらも腕は確かで、かつて、トゥパク・アマルが敵の巨大な半月刀によって致命的な大怪我を負った際、見事に手術を成功させ、完全回復に至らしめたという治療歴を持つ。
この時代、まだ麻酔というものが無く、それ故、受ける側も行う側も大手術はいっそう難儀を極めた。
それでも手術のメスを体に入れなければ治療はできず、手術を受ける患者は想像を絶する苦痛に耐えなければならない。
特に、あの時、トゥパク・アマルは甚大な負傷を負いながらも、意識が鮮明に保たれていた。
そのような彼の術中の苛烈な痛みを少しでも和らげようと、この老練な従軍医は、藁にもすがる思いで、ヒーリングの力を備えているらしきコイユールを助手に抜擢したのだった。
「あの時の手術のことを、トゥパク・アマル様が覚えておいででな」
治療場から離れた人目につきにくい回廊の石柱に身を寄せて、従軍医が低声(こごえ)で語り出す。
「あの日、おまえが、トゥパク・アマル様の患部の辺りに両手を当てて、 術中の痛みを軽減するためにヒーリングを行ったであろう。
あれが、それなりに効果があったと陛下はお考えのようなのだ」
「えっ…そ、そう仰って頂けるのは嬉しいですけれど…。
ですが、私、あのような大きな手術でヒーリングを行ったのは初めてでしたし、実際のところ、どれほど役に立ったか、正直、心もとないのです。
もし痛みが僅かでも軽くなってくれたなら、多分、それは先生の治療の技術やトゥパク・アマル様ご自身の精神力の強さのためであったと思います」
思いがけず過去の自然療法の話になって、コイユールは驚いて目を瞬かせたり、頬を上気させたりして、夢中で返答する。
そのようなコイユールを目元に皺を寄せて静かな眼差しで見つめながら、老医師は、噛み締めるように続けていく。
「いずれにしても、あの手術を成功させた時のように、また治療を頼みたい人物がいると、トゥパク・アマル様から直々にお達しがあったのだ。
わたしと、おまえにだよ、コイユール」
従軍医の真剣な表情に押されるように、息を詰めながら、コイユールが擦れ声で小さく問う。
「治療を頼みたい人物って、どなたなのですか…?」
「スペイン軍総指揮官、ホセ・アントニオ・アレッチェだ。
詳しい容態はまだ分からんが、全身火傷で、酷い激痛に喘いでいるらしい」
「ええ?!
ア…、アレッチェ…様の治療ですって…?」
さすがに驚愕して声を高めてしまったコイユールに、従軍医が素早く「シーッ」と口元に人差し指を立てて、彼女を諌(いさ)めた。
「おまえも知っての通り、インカ軍の兵は、多かれ少なかれアレッチェに恨みや悪感情を持っている者が多い。
そうした者たちの感情を刺激しないためにも、アレッチェの治療については、まだあまり大っぴらにしない方が良かろう」
慌てて両手で口を覆いながら、コクンと小さく頷くコイユールの顔色は、次第に青ざめていく。
この戦いが始まってから、どれほど多くの仲間のインカ兵や女性義勇兵たちが、アレッチェの指揮によって殺戮されてきたことだろう。
インカ軍の幹部でありトゥパク・アマルの重側近でもあったオルティゴーサやフランシスコも惨殺され、褐色兵の将フィゲロアがアレッチェの手によって直に銃殺される瞬間も目撃した。
いや、そもそも、アレッチェは、スペイン軍総指揮官として反乱軍討伐に乗り出す以前より、全権植民地巡察官として、副王ハウレギの膝下で、この植民地ペルーの支配に絶大な権力を振るってきた。
何重にも絞り取られる過大な税金、殆ど生きては戻れぬ過酷な強制労働、日用品を高額で売りつけられる強制配給など、植民地支配下におかれたインカの人々を苦しめ抜いてきた植民地政策に、直接的にも間接的にも、このアレッチェが関わっている。
まだ幼い日に、大好きだった両親の命を鉱山の強制労働で奪われたことも――。
コイユールの両親もまた、他のインカ族の者たちと同様、金銀採掘をさせられるため、故郷から遠く離れた鉱山へと駆り出さていった。
煉獄の火に焼かれるような苛烈な環境の中で、まともに食料も与えられずに長時間の重労働を強いられ続け、ついには命を落としたのだった。

すっかり俯(うつむ)いてしまったコイユールに、従軍医が静かに語りかける。
「コイユール、アレッチェの治療に関わるのが辛ければ、無理をしなくても構わないのだよ。
おまえの気持ちは分かるし、わたしからトゥパク・アマル様に上手くお伝えしておくから」
従軍医の気遣いに満ちた声が耳元に響き、コイユールはハッと我に返った。
「先生…私、なんだか動揺してしまって、自分がどうしたらいいのか……」
微かに震える声で答えながら見上げる彼女の目に、温厚ながらも悲哀を帯びた従軍医の皺深い面持ちが映る。
「よく考えてから決めればいい。
トゥパク・アマル様も、わたしも、決して強制しようなどとは思っていないのだから」
そう語るこの老練な従軍医こそ、この数年間に及ぶ反乱期を通じて、いや、もっと以前から何十年にも渡って、自分などが知るよりも遥かに悲惨な末路を辿ってこの世を去りゆくインカの人々をどれほど多く見送ってきたことだろうか。
「先生は、あの人の治療を引き受けるのですか?」
喰い入るように見つめるコイユールの黒曜石の瞳の中で、中肉中背の従軍医は、年齢の割に筋骨逞しい肩を軽くすくめてみせた。
それから、「さあ?どうしたものか」と、本気なのか冗談なのか分からぬ調子で苦笑する。
「とりあえずは、あの者の様子を見に行ってみて、それから決めても遅くはなかろう。
ということで、わたしは、これからアレッチェの居所に行ってみるが、コイユール、おまえはどうする?」
従軍医の問いかけに、コイユールは、しばし身を固めたまま、答えに窮している。
そんな彼女を見かねた医師が、「では、わたしが見てきたら、後で様子を教えてあげよう」と沈着な声音で言って、踵を返した。
「あ…、いえ、お待ちください。
ただでさえ先生はとてもお忙しいのに、そのようなお手間はおかけできません。
とにかく様子を見るだけでも、私もご一緒いたします」
砦の回廊を奥の間へと進んでいく己の後を小走りに追いかけて来るコイユールに、老医師は軽く振り向いて、頷いた。
かくして、アレッチェの治療室は、人目を避けるかのように、砦最上階の奥まった場所に定められていた。
その居室に至るまでの回廊の途中には、一定の間隔ごとに、厳格な面持ちをした逞しいインカ兵たちが幾人も配されている。
そのような衛兵たちの前を通り過ぎるたび、従軍医とコイユールは、彼らと目礼を交わし合う。
そうしながら、従軍医は、コイユールの耳元で、そっと囁いた。
「今のアレッチェは重体で、逃亡を図れるような元気はまだないはずだ。
だから、トゥパク・アマル様がここに多数の衛兵を配備した目的は、アレッチェの逃走を監視するためというよりも、むしろ、アレッチェに怨恨を持つインカ軍の者たちが衝動的にアレッチェを襲撃しに来ることのないよう、アレッチェを保護するためなのではないかと思う」
「そう…ですか……」
従軍医の言葉に驚きを隠せぬまま、コイユールは、また硬い石床に目を落とした。
(どうして宿敵中の宿敵のはずのアレッチェのために、トゥパク・アマル様は、ここまでなさるのだろう――)
無意識に己の右手を自分の胸元に置いて、そう心の中で呟いた。
胸の内の奥深い部分では、その答えがよく分かっているような、いや、やはり理解できぬような、いっそう混沌とした思いに囚われる。

そうしている間にも、彼女の耳元に、従軍医の少々緊迫した低音が響きくる。
「どうやら、あそこがアレッチェの居室らしい」
ハッと顔を上げたコイユールの視線の先15〜20メートルほどのところに、アレッチェの治療場と定められた個室の重厚な扉が見えてくる。
従軍医とコイユールは無意識のうちに互いを見交わし、意を決するように頷いた。
そして、さらに歩みを進め、アレッチェの居室に近づいていく。
すると、二人の到来に気付いた扉前の衛兵が、両腕でバッテンの動作をしながら、大きく首を振っている。
そんな衛兵の様子を訝(いぶか)しく思いつつ、従軍医たちが速度を緩めながらも進んでいくと、困り顔の衛兵が慌ただしい足取りでこちらに向かってきた。
「アレッチェの往診でしたら、今は無理です。
ご足労頂いて申し訳ないのだが、また出直してきてはくれまいか」
「今は無理とは?
アレッチェ殿に何か異変ですか?」
足を止めて、従軍医が重々しい口調で問う。
そんな二人のやりとりを見守るコイユールの心臓は、早鐘のように鳴り打ちはじめる。
(アレッチェの容態が予想以上に深刻で、もしや治療が間に合わなかったのでは…)
勝手な妄想が彼女の脳内を駆け巡り、胸の奥底がサーッと冷たくなる感覚に襲われる。
インカ全体の仇(かたき)とも言い得るアレッチェなどこのまま助からぬ方がいいのでは、という思いも正直あるはずなのに、それとは裏腹に、なぜ自分はこのように動揺するのだろう。
めまぐるしく転変する己の心にコイユールが翻弄されている間にも、従軍医は衛兵を押し退けて扉に向かって突き進んでいく。
そのような従軍医を、衛兵が急いで押し止(とど)めた。
「お待ちを!
今、中に入るのは危険です。
アレッチェが意識を取り戻したのだが、精神錯乱して、ひどく暴れているのです。
とても治療など受けられるような状態では――」
「ならば、余計、放っとくわけにはいかんではないか」
厳格な面持ちで言葉を返すと、高齢の体のどこにそのような力があるのか、自分の肩を押さえていた衛兵の剛腕を振り切って、従軍医は重い扉を押し開けた。
そのまま扉の中に踏み入っていく従軍医を、コイユールは殆ど反射的に追いかけていた。
この瞬間のコイユールにとっては、アレッチェの容態以上に、衛兵を振り切って室内に入ってしまった老医師の身の方が心配だったというのが本心である。
が、中に飛び込ん途端、彼女の視線は即座にアレッチェの方に釘づけられた。
「――!」
アレッチェの姿、とはいっても、今は、全くそれが誰なのか判別不能ではあったが――彼は、どこかで聞いた異国の怪物さながらに、足先から頭の天辺まで包帯でグルグル巻きにされていたのだ。
別の従軍医が施した一時的な応急処置なのであろうが、その姿はさすがに衝撃的なもので、室内に鏡が無くてよかった…と、アレッチェ自身が己の姿を目にすることがなくてよかったと、そう思わずにはいられぬような悲惨さであった。
その化け物じみた格好で、アレッチェは、周囲に群がるインカ軍の衛兵たちを、手足を振り回して薙ぎ倒し、蹴り上げながら、狂ったように暴言を吐き散らしている。
「蛮族どもめ、汚らわしい手でわたしに触るでない!
ええい、出せ!!
すぐにこの部屋から、わたしを出すのだ!
この砦は、わたしのものだ!!
おまえたちの勝手は断じて許さぬ!」
アレッチェといえば氷のように冷酷無比で悪略に長けた冷静な人物と聞き及んでいたのだが、今、目の前にいる人物は、感情剥き出しの上、己の置かれた状況さえも分かっていないかのような振る舞いである。
コイユールは、驚愕して立ち竦(すく)んだまま、ただただ茫然とアレッチェに見入っている。
一方、彼女の傍では、従軍医がアレッチェの一挙一動を観察しながら、沈着な声で呟く。
「過度に受け入れ難い現状や尋常ならざる全身痛で、さすがのアレッチェも自制の箍(たが)が外れているらしい。
とはいえ、あのグルグル巻き状態で、これだけ暴れる元気が残っているなら立派なものだ。
そもそも痛みをしっかり感じられること自体、火傷痕の神経が健在である証しでもある」
そう冷静に語る従軍医の言葉に朦朧(もうろう)と頷きながらも、コイユールは、まだ現状を受け留めきれずに、変わり果てた眼前の敵将を見つめたまま微動だにできない。

不意に、そんな彼女とアレッチェの視線が合った。
アレッチェは、いよいよ怒り爆裂な様相で、包帯の隙間から覗く二つの黒眼を鬼のように険しくさせる。
「インディオの下賤な女が、なぜここにいる?
しかも、なんだ、その生意気な目は?!
このわたしを誰だと思っている?
それとも、何か?
あのトゥパク・アマルが、軟禁したわたしへのせめてもの慰めに、おまえを充(あ)てがったということか?
ならば、このような貧弱な小娘ではなく、もっと豊満な美女を連れて来い」
衛兵たちに取り押さえられながらも、そう嘯(うそぶ)いて口端を吊り上げたアレッチェの双眸が、蛇のようにコイユールに絡みつく。
その両眼の放つ、底知れぬ憎悪を滾(たぎ)らせた残忍さと、強欲にまみれた禍々しい黒光を前にして、コイユールは完全に凍りついたまま、顔面蒼白になっている。
他方、アレッチェの意識がコイユールに向いた瞬間を捉(とら)えて、従軍医は素早くアレッチェの後ろに回り込んだ。
両腕を衛兵に押さえ込まれながらも、そのボロボロになった体のどこから湧き出るのかと驚嘆させられるほどの怪力で、アレッチェは獣のように咆哮する。
「どいつも、こいつも、いけ好かぬ!
このような端女(はしため)にまで侮辱を受けようとは!!」
「侮辱だなんて…そんなつもりはありません…!
お願いですから、どうか今は安静にして、体を休めてください」
震え声ながらも噛み含めるように言葉を返したコイユールに、かえって感情を逆なでされたアレッチェが、猛然と両腕の衛兵を振り飛ばして、こちらに突進してくる。
「この端女郎が誰に物を言っている!!」
『APU…KONTITI…TEQ……!』
身じろぎもできぬままに、それでもコイユールは、涙の滲んだ瞳を決然と上げて、反射的に、インカのケチュア語で祈りのマントラを唱えていた。
と同時に、アレッチェの背後にいた従軍医が、懐から治療用の棍棒を取り出し、それをアレッチェの首後ろ目掛けて振り下ろす。
「――グァ…ッ…!」
アレッチェが低く嗚咽を漏らして、石床に崩れ落ちた。
長身のアレッチェに対して、中肉中背の老医師の目の高さは、ちょうどアレッチェの首付け根辺りであり、棍棒は狙いを外すことなく、相手の頸椎を一撃で突いていた。
しかも、充分な「気」を込めて――。
インカでは、古来より、エネルギー循環やパワーを高める独特の呼吸法が受け継がれており、戦士、医師、シャーマン、ヒーラーなど、皆、己の「気」を高度に増幅することにも長けている。

「さてと、これで、しばらくは気を失ったまま、大人しくなるでしょう。
皆さん、手を貸してください。
この暴れん坊将軍殿を寝台に運びたいので。
ああ、そっと、頼みますよ」
温和な口調で言う従軍医の言葉に、衛兵たちも平静を取り戻し、床に倒れたまま気絶しているアレッチェを慎重にベッドへ運んでいく。
やっと静寂の訪れた室内で、アレッチェの全身状態を一通り診察し終わった従軍医が、ふっと、溜息とも安堵ともとれる息をついた。
薬草を丁寧に塗布し、清潔な包帯をアレッチェの体に巻き直していたコイユールが、医師の方へ顔を上げる。
「先生、アレッチェ様の容態は、どうなのでしょうか?」
「うむ、しばらく治療を続けて様子を見なければ、まだ何ともな…。
火傷は確かに重症だが、良くも悪くも、体力も精神力も不気味に強靭な人物だ。
それもこれも猛烈な執念によるところかもしれんが、何にしろ生きる力にはなろう。
それに、多分、火災の現場で、火から庇(かば)われた様子も見られる」
「火から庇われた…?
それでは、その時に一緒にいらしたトゥパク・アマル様が?」
息を詰めて呟いたコイユールに、従軍医は持参した数種類の植物粉を調合し、手早く追加の薬をこしらえつつ頷いた。
「あのお方のことだから、身を挺して、アレッチェ殿を周りの炎から庇ってやったのに違いあるまい。
そうでなければ、この者がどんなに強者(つわもの)であろうとも、こんな、九死に一生を得るような可能性は皆無だっただろう。
もっとも、まだ助かるかどうかは分からんが」
自分の言葉にすっかり引き込まれて手の止まっているコイユールに、老医師は、続きの包帯を巻くように、と視線で促す。
我に返って再び包帯を手に取りながら、コイユールは、アレッチェの掘深い横顔をうかがった。
包帯の隙間から覗く瞼は固く閉じられ、意識を失ってもなお激痛と戦っているのだろう、ピクピクと苦悶に満ちた痙攣(けいれん)を続けている。
「それで、コイユール、どうする?
アレッチェ殿の治療のことだが。
どうも、今回は、おまえは関わらない方がいいような気がするのだよ」
躊躇(ためら)いがちに問う従軍医の言葉が、耳元で響いた。
「先生……」
返答に詰まっている彼女の脳裏に、先刻、物凄い剣幕で激昂し、己の方に驀進(ばくしん)してきた、あの鬼のようなアレッチェの形相が生々しく甦る。
と共に、あの時の身も凍るような恐怖もフラッシュバックしていた。
あの鬼気迫る勢いで、彼の鋼鉄のような腕で張り倒されていたら、恐らく、自分など、ひとたまりもなかっただろう。
気絶して横たわるアレッチェの全身から、今も禍々しい冷気が放たれているようで、居室全体が異様に冷え冷えと感じられる。
全身に走る寒気を振り払うように、コイユールは、包帯の端をしっかり結び直した。
「いえ、私にお手伝いをさせてください」
「コイユール!
此度は、無理をしない方がいい。
この者は、我らが思っている以上に…」

しかし、まだ青褪めた顔色のまま、それでも、彼女は覚悟を決めた表情で、きっぱり首を振った。
「いいえ、トゥパク・アマル様が、ご自身の身を挺してまでも、護ろうとしたお方なれば――!」
雷雨が次第に静まりだしたのは、さらに夜も更けた頃であった。
晩餐の間では、食事を終えたトゥパク・アマルやアパサたちが会話を続けていたが、その内容は、おのずと作戦会議のような様相を呈してくる。
トゥパク・アマルを中心に、アンドレス、アパサ、ビルカパサ、ロレンソ、マルセラらが、引き締まった表情で、その座を共にしていた。
先ほどまで数々の心尽くしの料理が並んでいた食卓の中央には、今は、大きな地勢図が広げられている。
その地勢図をスラリとした指でなぞりながら、特に普段はその場にいないアパサに対して、トゥパク・アマルが現在の布陣と戦況を簡潔に説明していた。
「この期に至っては、もはや戦線は国全体に拡大し、我が軍もスペイン軍も兵力は著しく拡散している。
拡散した分、各所的には手薄になってしまった互いの兵力の隙を突いて、予断のならぬ奇襲戦が頻発している。
つい数日前には、我らの本陣であるサンガララが手薄になったところを狙われ、敵の急襲を受けたが、ミカエラやベルムデス殿の采配で、こちらは敵軍を撃退することに辛うじて成功した。
そのような状況下でも、此度の戦いで最も要(かなめ)となる地は、変わることなく、インカの聖都クスコと首府リマである。
いかに兵力が分散しているとはいえ、要衝のこれらニ都市には、両軍共に重装備の大軍を動員している。
クスコ奪還のために現地に赴いてインカ軍を統率しているのはディエゴだが、対峙しているバリェ将軍率いるスペイン軍も強壮で、双方の力が拮抗(きっこう)したまま、未だ決着がつかずにいる。
一方、副王ハウレギをはじめスペイン役人の巣窟とも言える首府リマには、クリオーリョ(植民地生まれのスペイン人)の革命軍を指揮するシモン殿が向かっている」
「クリオーリョの革命軍だと?!
そんな白人どもの部隊なぞ、当てにできるのか?」
椅子にふんぞり返ったまま、目を剥いて吐き捨てるように言い放ったアパサに、トゥパク・アマルが、ぐっと顎を引いた。
彼は、研ぎ澄まされた眦(まなじり)に燭台の光を反射させながら、力を帯びた艶やかな低音で応ずる。
「シモン殿は信用に足る人物だ。
スペイン渡来の白人たちの独裁的な支配や偏見に、当地生まれの白人たちは強い反発を抱いているが、シモン殿は、彼らの不満や怒りを変革のためのエネルギーへと昇華する術(すべ)をよく心得ている。
さらに、彼は、この地に暮らす全ての者たちが、スペインやインカなどという枠を超えて手を携え、共に平和に、共同創造して生きていくという理念を、わたしと共有している」
トゥパク・アマルの言葉に聞き耳を立てながらも、アパサは、片眉を吊り上げ、胸の前で組んだ筋骨逞しい両腕をさらに強く組み直した。
「この戦場から尻尾を巻いて逃げ出したアラゴンの行き先は、親父の副王ハウレギがいるリマに決まっている。
そのアラゴンやハウレギの息の根を止め、リマを陥落させない限り、俺たちに真の勝利は無い。
実際、白人の革命軍なぞ当てになるのか怪しいもんだし、反乱の成否を決める最重要地に、いかにも手薄すぎやしねぇか?」
「アパサ殿の仰るように、トゥパク・アマル様も首府リマ攻略の重要性は重々心得ておられます。
ただ、ここアレキパでの英国艦隊やスペイン軍との決戦もありましたので、一時(いちどき)に、全要衝地に必要十分な兵力を配備することは難しかったのです。
それはスペイン軍とて同じことだと思われます。
当地での戦いがこのまま沈静化するようであれば、当地の部隊をリマに逐次投入していく計画だったのです」
トゥパク・アマルの代わりに答えたアンドレスを一瞥(いちべつ)して、「だが、英国艦隊が、また襲撃してこないとは言えねぇよな?」と、アパサが憮然として切り返す。
その場の全員が息を詰め、暫し重い沈黙が場を支配した。
その沈黙を破って、双眸をギラギラ光らせながら、アパサがまた口を開く。
「全滅を免れた英国艦隊が、このまま大人しく母国に引き返すと思うか?
英国艦隊の総指揮官がどんな男か俺は知らんが、このまま引き下がるようなヤツなのか?
そいつが戦死したとか、囚われたとかいう情報はあるか?
俺たちインカ軍がこの砦を制覇したと知れば、英国艦隊などと戦ったことのない俺たちが相手なら今度こそ勝機ありと見て、態勢を立て直し、舞い戻ってくるかもしれんぞ?
そんな状況下で、トゥパク・アマル、おまえたちは即座にはこの場を動けまい?」
ぐっと息を呑んで己の言葉に聴き入ったまま、こちらに強く集中している面々に、アパサは、また鋭い視線を走らせる。

しかし、今度は、彼にしては珍しく、かなり真面目な面持ちに変わると、おもむろに姿勢を正した。
そうしてから、アパサは真正面に座しているトゥパク・アマルの方へ炯々と燃える両眼を据え、誓約を立てるかのように厳然と言う。
「トゥパク・アマル、リマのことは、この俺に任せてくれないか。
少しの間、部下たちをこの砦で休めたら、俺と俺の部隊は、リマに向かう。
そして、今度こそ、アラゴンとの決着をつけてやる。
アラゴン率いるスペイン王党軍は、父王ハウレギ直下の最重要部隊でもある。
アラゴンを倒せれば、ハウレギを倒すことにも直結する。
もちろん、簡単な相手じゃないことは、俺にも良く分かっている。
だが、時間も無い、兵力も限られている、尚且つ、おまえたちは、すぐにはここを離れられない。
ならば、自由に動ける俺が行くのは道理だろう。
おまえたちとて、異論はあるまい?」
暫し、思慮深げに切れ長の目を細めて静かにアパサを見つめていたトゥパク・アマルが、やがて、ゆっくり口を開いた。
「アパサ殿、そなたがリマに行ってくれると言うのであれば、それは願ってもないことだ」
「よしっ!
それでは、話は決まりだな」
嬉々として叫んだ勢いで、机上をダンッと叩いたアパサに、トゥパク・アマルが沈着な面差しで続ける。
「しかしながら、アラゴン軍の重装備は、さすがに副王ハウレギ直下の部隊だけあって、只ならぬ強壮なものであった。
此度の戦場では、アパサ殿の援軍が到来してくれたおかげと、幸運にも荒天に恵まれ、我らは一命をとりとめたが、そうでなければ我が軍は全軍壊滅させられていたかもしれぬ」
重々しく語るトゥパク・アマルの言葉に、彼の隣に席を占めているビルカパサが、鷲鼻のきわだつ厳めしい面持ちを深く頷かせた。
先刻の戦いで、最前線に立ってアラゴン軍の凄まじい砲火に身を晒していたビルカパサは、まるで燃える隕石群の襲撃のごときアラゴンの猛攻撃を、今また肌身に思い出して眉間に強く皺を寄せている。
そのようなトゥパク・アマルやビルカパサに、ムッと、険しい目線を走らせ、アパサが「つまり、俺では役不足だと言いたいのか?」と、吐き捨てた。
「そうではない。
それほどの強靭な相手だからこそ、そなたのような猛将が、リマに向かってくれることは有難い。
なれど、そなたのような者に言うのはおこがましいが、あのアラゴンを相手に正面突撃を敢行するのは得策とは限らぬ。
此度の戦いで、そなたの部隊も被害を受けており、そなたの兵たちに過度な負担がかかることも案じられる。
リマの副王やアラゴンへの対応はわたしにも思うところがある故、わたしとの連絡を密に取り、連携して事を進めると約束してほしい。
それから、先ほど話したクリオーリョの革命軍とも、接触を図ってほしい。
そして、そなたが、シモン殿と直に会い、彼が信頼に足ると、手を携えるに相応しい相手だと納得したなら、彼とも力を合わせてほしいのだ。
それに、当地やクスコの戦況を見極めながら、我らもリマへの増援は当然ながら出す心積もりもある」
「なんだか要求が多くないか?
ま、よかろう、おまえのクダクダとした条件は分かった。
だが、おまえの対応策とやらも、白人の革命軍のことも、俺がその通りにするかどうかは、あくまで俺が納得すればのことだ。
しかし、もちろん、俺とて、インカ側にとって最善の結果を導きたいと思っている。
だから、トゥパク・アマル、おまえこそ、俺を信用しろよ?」
「もちろんだ」
決然と応えたトゥパク・アマルの視線と、貫くように見据えるアパサの視線が、ガッチリと合う。
二人は、蒼く燃える瞳を真っ直ぐに見交わし合ったまま、力強く頷いた。

高まる闘志によって熱気を帯びた室内に、再び幾ばくかの静寂が訪れた後、今一度、アパサが口火を切った。
「そうえば、捕えたアレッチェは、今、どうなっている?」
また挑むような炯々たる眼(まなこ)で己の方に身を乗り出してきたアパサに、軽く目をやってから、トゥパク・アマルは己の顔にかかった前髪をサッと指先で払った。
それから、言葉を選びつつ、簡潔に答える。
「アレッチェ殿は、全身火傷で、意識不明の重体になっている。
従軍医の治療を受けているはずだが、あの状態では、再び持ち直すかどうか疑わしい」
「なっ…治療だと?
あんな奴に治療など施してやる必要などない!!」
アパサの頭髪が怒気をはらんでカッと逆立ち、またも広間に緊迫した空気が張り詰めた。
そのような場の雰囲気を察し、すかさずビルカパサが、断固としながらも真摯な物腰でアパサに応ずる。
「アパサ殿、貴殿もよく知っての通り、我らインカ軍は、たとえ捕虜であろうとも、負傷している者には然るべき治療を施すことが古来からの習わし。
それは、敵の将兵とて、例外ではありません。
――それよりも、リマへの貴殿の進軍のことですが、トゥパク・アマル様のご決定とあらば、わたしも異論はありません。
ただ、ラ・プラタ副王領の守備が手薄になることが、やはり気懸りではあります」
アレッチェの処遇を巡ってまたも一悶着起こりそうなところを、機転を利かせて素早く話題をすり替えたビルカパサに、アンドレスやロレンソたちは、内心、ホッと息をつく。
長時間に渡る苛烈な戦いを経たことによる鉛(なまり)のような疲れが、激しい睡魔と一緒にドッと押し寄せてもいたのだ。
雷雨に濡れた体を乾かすためにくべていた暖炉の火が広間の空気をほどよく暖め、パチパチとはぜる火の粉の音が子守歌のように心地よい。

アパサさえも、まだ何か言いたげに鼻腔をヒクつかせながらも、満腹感と共に襲い来る強い疲労と眠気には抗(あらが)えず、ついに大あくびを放った。
と見るや、椅子にふんぞり返って、まだ何やらブツクサ言いつつも、ウツラウツラと舟を漕ぎだした。
そのような面々を、柔らかな光を湛えた目を細めて見渡し、トゥパク・アマルが散会を命ずる。
「ラ・プラタ副王領には、その周辺地域に派兵している者たちの中から、増援部隊を送るよう手配いたそう。
さあ、もう夜明けも近い。
今夜はこれにて散会といたす。
皆、此度も誠によく健闘してくれた。
充分に休養をとってくれたまえ」
その夜の会合が散会となり、各人がおのおのの休息場所へ引き上げていくと、トゥパク・アマルに挨拶をしてアンドレスも晩餐の間を後にした。
そのまますぐにも寝台の上に倒れ込みたいような心境だったが、それでも、どうしても気になることがあった。
先ほどアパサも話題にしていたが、あのアレッチェのその後の容態である。
(アレッチェのことに関して言えば、アパサ殿の気持ちが俺にもよく分かる。
あいつのおかげで、俺たちインカの人間はさんざん苦しめられてきた。
だから、このままアレッチェがスペイン軍からいなくなってくれたら、正直、インカ軍にとってはすごく有難いことだと言える。
そんなアレッチェをトゥパク・アマル様は敢えて助けようとしているのだから、アパサ殿が憤慨するのも無理はない。
ビルカパサ殿の言うように、捕虜の治療はインカの昔からの習わしだと言えばそれまでだが、それにしたって、あのアレッチェを回復させて、一体、トゥパク・アマル様はどうなさるおつもりなのか?)
アンドレスは琥珀色の大きな瞳を微動させながら、強く唇を噛み締めた。
(やはり、たとえ手を尽くしても、重体のアレッチェがこのまま逝ってくれたら…。
最善を尽くしても駄目ならトゥパク・アマル様だってご納得されるだろうし、スペイン人たちにも一応の義理が立つ上、アパサ殿のような考えの者たちにも不満が残らないだろう。
だけど…、そうなったら、そうなったで、本当にそれでいいんだろうか?)
いつしか眉間にきつく皺を寄せて、そこまで勝手に思考を逡巡させてから、アンドレスはブルブルッと頭を振った。
「ああ、また俺の悪い癖だ。
周りの皆が丸く収まることばかりを考えてしまう。
それよりも、もっと大事なことは、インカにとって真に最善の状態が実現するには、どうしたらいいのかってことなのに!」
無意識にそう声を張ってしまってから、アンドレスは慌てて口を押えた。
シンと静まり返った深夜の回廊に、己の声が高らかに木霊する。
その殷々(いんいん)たる響きが鼓膜を震わせるのを耳に感じながら、彼は寝所に向かっていた足をピタリと止めた。
それから、踵を返して、重石を乗せられたような疲労体を引きずりつつも、アレッチェの治療場に向かって歩みだす。
(とにかく、このままじゃ眠れない。
アレッチェの今の様子だけでも把握しておきたい)

長時間に渡った激戦による途方もない消耗で、五体満足な者たちも、負傷した者たちも、皆、眠りに落ちているようで、真夜中の砦は深海のように静まり返っている。
それでも、不意を突いた敵襲や砦内の変事に、即、対応できるよう、健康体のインカ兵たちはローテーションを組み、砦内や周辺地域を見回り、または、武装姿で待機している。
回廊で時々すれ違う巡回のインカ兵と目礼を交わしながら進むうち、やがてアレッチェの居室の厚い扉が見えてきた。
扉前に立つ衛兵たちに挨拶をして、アンドレスは「中に入っても?」と、彼らに問いかける。
「どうぞお入りください。
少し前までずいぶん暴れていたんですが、今はおとなしく眠っています」
「アレッチェが暴れた?
あの大火傷の重体で?」
衛兵の言葉に、アンドレスは耳を疑い、息を詰める。
そのような彼の面前で、衛兵たちは肩をすくめて「そうなんです」と、溜息混じりに答えた。
「我々が何人もで押さえ込んでも、それを振り飛ばす勢いで、そりゃ、もう大変だったんです」
「君たちを振り飛ばした?」
いよいよアンドレスは両の目を大きく瞬(しばたた)かせた。
アレッチェの警護に配されただけあって、ここにいる衛兵たちは、長身のアンドレスを凌ぐほどにひときわ身の丈が高く、体格もガッチリと強靭で逞しい。
そんな兵たちが、さらに肩をすくめて、頷いた。
「いやはや、まいりましたよ。
まあ、あの時のアレッチェは、ひどく興奮していましたので、それもあって、常軌を逸した馬鹿力が出たのかもしれませんが」
このような場所の警護を任された衛兵たちを改めて気の毒に思いながら、アンドレスは、心から彼らの労をねぎらわずにはいられない。
「そんなことがあったなんて、本当に大変だったね」
「幸い、従軍医が一撃で気絶させてくれたんで、あの場は、なんとか収まりましたが。
ですが、あの者は、あんな全身包帯巻き状態でも、少しも油断はなりません。
アンドレス様も、アレッチェに近づく時は重々お気を付けください」
「分かった、そうするよ、ありがとう。
それにしたって、従軍医も大変だったな。
先生はもう寝に行かれたんだろうか?
それとも、まだ中に?」
重々しいドアの取っ手に手をかけながら入室しようとするアンドレスに、衛兵たちが、彼の背後から答える。
「いえ、従軍医は、他の重患たちが何人もいますので、一旦、大広間の治療場に戻っています。
今は、アレッチェは完全に気を失っていますので、付き添いは看護の義勇兵が一人です」

その衛兵の言葉に、アンドレスは急激に嫌な予感に憑かれて、思わず頬を引きつらせた。
「看護の義勇兵だって?
ま、さか、その義勇兵って…」
喉元までコイユールの名が出かかったが、アンドレスはそれを呑み込み、急いでドアを押し開けた。
(やっぱり……!)
室内に広がる光景を目にして、アンドレスは、胸の辺りがサーッと冷たくなるのを感じていた。
室内は四隅に置かれた燭台に照らされているが、それでも不気味に薄暗く、妙な冷気が漂っている。
その異様な気配の空間に据えられた寝台には、ミイラのような姿のガッチリした男のシルエットが横たわっている。
恐らく、あれが、意識を失って眠っているアレッチェであろう。
そして、彼の寝台の横には、息を潜めて患者の状態を見守る一人の年若い娘が、ひっそりと小椅子に腰かけている。
長いおさげで縁取られた彼女の横顔はひどく青ざめており、その全身も微かに震えているかのように見える。
アンドレスは、居た堪れぬ心境で背後のドアをそっと閉めると、彼女を怯えさせることのないように、できるだけ静かな足取りでそちらに近づいていく。
「――コイユール」
驚かさないように囁きかけたつもりだったが、それでも、コイユールは、ビクッ、と細い肩を揺らして、驚きの表情でこちらを振り向いた。
が、そこに現われたのがアンドレスだと分かると、深い安堵の表情で、花の蕾がほころぶように微笑んだ。
「アンドレス、どうしたの?
アレッチェ様の様子を見に来たの?」

しかし、アンドレスは、強烈な心配の念と、それが高じて怒りにも似た感情が突き上げ、どうにも厳しい顔つきと口調になってしまう。
「どうしてだよ?
なんでコイユールが、こんなところに回されているんだ?
こいつが、どんなに危険人物なのか、分かってるのか?
もしや…トゥパク・アマル様か?
以前、君がトゥパク・アマル様の看病をしたのと同じように、今度は、アレッチェを世話するようにと、そうトゥパク・アマル様が命じたのか?」
真っ青な顔色で両眉を吊り上げ、責めるように詰め寄ってくるアンドレスに、コイユールは動揺して、オロオロと立ち上がった。
そうしながらも、彼女は、シーッと、相手の口元に人差し指を立てる。
それから、アンドレスの耳元で、小声で囁いた。
「アンドレス、そんなに大声を出したら、せっかく眠ったアレッチェ様が目覚めてしまうわ。
それより、アンドレス、ここに座って。
どんなに二人でこうして逢いたかったか」
それでも、アンドレスの昂ぶった感情は収まらない。
「コイユール、君はトゥパク・アマル様のことをすごく崇拝しているから、だから、いつもトゥパク・アマル様の言葉にはどんなことでも従うんだ。
だけど、今度ばかりは見過ごせない。
こんな危ないところを一人で任されて、何かあったらどうするんだ?
今すぐ、俺からトゥパク・アマル様に話して、こんなところにいなくて済むようにしてやる!」
そう憤然と息巻いて部屋から飛び出していきそうなアンドレスを、コイユールの華奢(きゃしゃ)な腕が懸命に押し止める。
「アンドレス、そんなこと、止めて!
普段は従軍医の先生も一緒だし、いられる時は私以外の看護の義勇兵もちゃんと付き添ってくれることになってるの。
それに、トゥパク・アマル様に強要されたわけじゃないわ。
私が、アレッチェ様の看護をやるって決めて、自分の意志で引き受けたのよ」
コイユールが、あまりにも必死に止めるため、さすがにそれを乱暴に振り切ることはできず、アンドレスの方が足を止めた。
「今、扉の外で聞いたんだが、あのガタイのいい衛兵たちでさえ降り飛ばされるほど、アレッチェは暴れたっていうじゃないか。
こんな包帯姿になっていても、こいつは全く何をしでかすか分からない危険極まりないやつなんだぞ。
これまでだって、こいつが先頭に立って、どんなに汚い手口を使って、インカ兵や民衆を苦しめ、殺戮してきたか、コイユールだって、ずっと見てきたじゃないか。
こいつは、トゥパク・アマル様にとっても、俺たちインカ軍にとっても、インカ族全体にとっても、最大の宿敵の一人と言っても過言じゃない」

「だけど、そんな影響力のあるスペイン側の指導者だからこそ、アレッチェ様のお心が変われば、この戦いをお互いにとって良いかたちで終わらせるきっかけになるかもしれないわ」
黒曜石の瞳を揺らしながら懸命に訴えてくるコイユールを見下ろすアンドレスの口元からは、思わず溜息が漏れる。
「コイユール、苦しそうにしている重症患者をほっとけない君の気持ちは分かる。
だけど、こいつは、そういう善意が通じる相手じゃないんだ。
従軍医や君たちがどんなに骨身を削って治療や看病をしたとしても、もし仮に、そのおかげで命が助かったとしても、アレッチェの性格や考え方が変わるなんて思わない方がいい。
そんな期待を持って接していたら、逆につけこまれ、利用されて、奈落の底まで突き落とされるぞ」
そう言い放ってしまってから、アンドレスは、急に喉がつかえて、口をつぐんだ。
毒を吐くような自分の言葉に、己の心の中に蠢くアレッチェへの激しい憎悪の感情を改めて目の当たりにする思いがしたのだ。
アレッチェに特有の属性だと思っていた忌まわしい残虐性や身勝手な偏見が、実は、己自身の中にもあるのだと自らが自らに突き付けてくるようで、ひどく胸苦しくなる。
そんなアンドレスの内心を察してか、否か、いつしかコイユールのしなやかな手が、そっと、彼の手を包んでいた。
「私のことをこんなに心配してくれて、ありがとう。
アンドレスの言う通り、アレッチェ様が一筋縄なお方でないことは、私も分かっているつもりよ。
どんなに看病しても、アレッチェ様のお心が変わることなどないかもしれない。
それに、私の中にも、アレッチェ様への憎しみが無いと言ったら嘘になるわ。
だけど、このままでは、私自身が苦しいの。
誰かを憎んでいるって、苦しいし、悲しいし、とても辛い…。
そんな自分に対しても自己嫌悪してしまうの……。
だから、私は、私自身が変わるためにも、アレッチェ様の治療に関わりたいのかもしれないわ」
ハッと我を取り戻して再び見つめ返すアンドレスの視線の先で、コイユールもまた、真摯な眼差しで、真っ直ぐこちらを見上げている。
「アンドレス、あなたは、皆が平和に幸せに暮らせる日がくるように、自分の命も惜しまず、いつだって全身全霊で力を尽くしてる。
だから、私も、せめて私にできることを精一杯やりたいだけなの」
「コイユール――」
その刹那、コイユールの瞳から、一滴(ひとしずく)、真珠のような涙が零れ落ちた。
どうしようもない愛おしさと切なさと、言葉にならぬ様々な感情が込み上げ、次の瞬間、アンドレスの両腕は、反射的にコイユールの全身を抱きすくめていた。

「きつい言い方をして、ごめん。
本当は、俺も、どうしたらいいのか迷っているんだ……」
彼の温かな腕の中で、コイユールは幾度も頷き、相手の背に回した腕に優しく力を込めた。
やがて名残惜し気に互いの腕をほどくと、コイユールに促されるままに、アンドレスは彼女の隣の椅子に腰かけた。
心の中は、まだ様々な思いで波立ったままではあったが、そんな彼の目から見ても、眼前で横たわるアレッチェの様子は形容しがたいほど惨(むご)たらしいものであった。
頭から足先まで包帯で巻かれ、呼吸は浅く苦し気に乱れ、不規則に苦悶の呻きを上げている。
「アレッチェの容態を従軍医は何て?
助かる可能性はありそうなのか?」
声を殺して問うアンドレスに、コイユールも囁き声で答える。
「普通の人なら助からないような重体だけど、アレッチェ様は体力や精神力が並みじゃないから、可能性はゼロじゃないって。
ただ、まだ危険な状態には変わりないから、どうなるかは治療を続けてみないと分からないって」
「そう…か」
アンドレスが低く唸るように答える間にも、コイユールは、苦しそうに悶えているアレッチェの腕や顔、足、上半身などにそっと両手を添えて、じっと精神を集中しはじめている。
彼が子供の頃から何度も目にしてきたコイユールの自然療法である。

この反乱が幕を開ける前、アンドレスの屋敷があった街のはずれに、ひっそりと祖母と暮らしていたコイユールは、幼い頃からこの療法を行っていて、街でちょっとした噂になっていた。
その噂を聞き付けたアンドレスの母親が、彼女自身の治療のためにコイユールを屋敷に招いたのが、アンドレスとコイユールの出会いのきっかけだった。
先祖代々から伝わるというその癒しの秘儀は、患者の患部に手を添えて、ケチュア語のマントラを唱えながら、手の平から、「気」のような、ある種のエネルギーを相手に送り込んでいくという。
そうすることよって、患部の痛みをやわらげたり、精神的な苦悩を解きほぐしたり、穏やかな安眠へと導いたりするのであった。
まだ科学的な根拠が示されているわけではないから、気のせいにすぎないという者もいるが、こうして見ていても、アレッチェの苦痛の呻きは徐々に小さくなっていく。
それにしたって、まさかコイユールがアレッチェに療法を施している姿を見ることになろうとは。
アンドレスは、どうにも拭い去れぬ重苦しい思いを胃の辺りに覚えながら、心の内で独りごちた。
(やると決めた以上、コイユールも従軍医も、本気で取り組むだろう。
それに、トゥパク・アマル様のことだから、ただコイユールたちに任せっぱなしということはないはずだ。
トゥパク・アマル様ご自身も、アレッチェの回復を促すために、さらなる方策を何か考えているかもしれない。
そんな皆の力が結集して、もしアレッチェが本当に一命を取り留めたとしたら――。
だとしても、こんな酷い火傷や怪我を負ってしまっては、重大な後遺症が残ることは避けられまい。
アレッチェのこの包帯の下は、一体、どうなっているのだろうか…)
アレッチェの体に巻かれた厚い包帯に手を添えて、懸命に意識を集中し続けているコイユールの真剣な横顔を見守りながら、アンドレスは固唾を呑んだ。
(もともとアレッチェは、表情こそ残忍できつかったが、精悍とも見える西洋人らしい整った顔立ちをしていたし、遠目からも人目を引く立派な体躯の持ち主でもあった。
戦場での動きを見る限り、運動神経もかなり優れていた。
それらが失われたら、たとえ生き残ったとしても、かえって荒(すさ)んだ状態になりはしないだろうか。
プライドの異常に高いアレッチェに、そのような自分自身が受け入れられるのだろうか……)
様々な思いや感情が、アンドレスの脳内や胸中を駆け巡り、堆積していた疲労に追い打ちをかける。
アンドレスは、心の奥底で、深く溜息をついた。
(本当に、一体、何が、どうなったら、一番良いのか――)
どうしようもない猛烈な脱力感が襲ってきて、彼の頭は、次第に真っ白に霞んでいく。
薄れていく意識の中で、とにかく今夜はもう、体力も、思考も、限界だと思った。
「コイ…ユール……」
朦朧とした擦れ声が耳元で響き、コイユールがハッと隣を振り向くと、アンドレスの上半身がグラリと揺れた。
どうやらアンドレスは、腰かけたまま眠りに落ちかかっているようで、彼女は慌てて、アレッチェに添えていた両手をアンドレスの方に移動させて、彼の体を支えた。
(長時間に渡る大変な戦いを経てきたのだもの、無理ないわ)
華奢な体つきのコイユールにとっては、今ではすっかり背丈も伸びて逞しくなったアンドレスを支えるのは一苦労である。
彼女は、そっと自分の肩も寄せて支柱にしながら、両手で相手の体躯を支え、小声で囁きかける。
「アンドレス、ちゃんと自分のお部屋に戻って休んだ方がいいわ。
もう夜明けも近いし、明日もきっと忙しいわ。
しっかり体を休めておかなければ、いくらアンドレスでも、もたないわよ」

そんなコイユールの優しい声と温かなぬくもりを遠のく意識の中で感じて、アンドレスは、さらに安息の眠りの中に落ちていく。
「コイユール…、アレッチェの看病を…俺は、まだ…納得したわけじゃない…んだ…」
己の肩にもたれかかったまま寝言のように呟くアンドレスに、コイユールは、静かに目を細めて頷き、小さく囁いた。
「分かったわ。
そのことは、また今度、話し合いましょうね」
自分の言葉が聞こえているのか、いないのか、ウトウトしながら、やすらかな寝息を立てているアンドレスの横顔を、やわらかな光を湛えたコイユールの瞳がそっと見守る。
「困ったわ。
こんなところで眠ってしまっては」
そう呟きながらも、アンドレスの存在をこんなに傍近くに感じる二人きりの静かな時間は、何ヶ月ぶりだろうか、いや、何年ぶりかもしれない、と心の奥で感じていた。

幾つもの戦火をくぐり抜け、すっかり軍人らしい精悍さを増したアンドレスの風貌だが、今、目の前にある無防備な寝顔は、幼い日と変わらぬ無垢な天使のようである。
(このまま、時が止まってしまえばいいのに)
甘美なせつなさが、コイユールの胸を締め付ける。
その時、不意に、突き刺すような鋭利な視線を感じて、彼女は咄嗟に我に返った。
誰かがこちらの様子をじっと窺(うかが)っているような感じを覚えたのだ。
先ほどまでの甘い感傷は吹き飛び、逆に不穏な予感が胸中に広がっていく。
コイユールは息を詰めて、寝台の方へと視線を馳せる。
そして、ビクリと身を竦(すく)めた。
薄闇の底に重く沈むように横たわるアレッチェのガッシリした体。
その顔に巻き付けられた包帯の隙間から、異様な光を放つ暗黒色の瞳が、微動だにせず、こちらを凝視しているように見えるのだ。
急に背筋が寒くなって、コイユールは小さく身震いした。
それでも、今一度、寝台の方に目を凝らすも、僅かな燭台しか灯っていない深夜の室内は視界が利きにくく、アレッチェが眠ったままなのか、目を見開いているのか、はっきりと判別ができない。
だが、闇の中で獲物を狙う蛇の目が虎視眈々とこちらを観察しているような、どうにも落ち着かぬ感覚がコイユールを捕らえて離さなかった。
そのことをアンドレスに伝えようと、うたた寝している彼の袖をコイユールが引っ張った時、急に大きな音と共に部屋の入り口の扉が開いた。
と思いきや、困り顔の衛兵が部屋の外から姿を現し、アンドレスの方へ声を張る。
「アンドレス様、治療場でケンカだそうです!
悶着が収まらないようで、現場が困っています」
大きな扉音や衛兵の声で目を覚ましたアンドレスが、「分かった、すぐに行く」と、まだどこか朦朧としながらも返答する。
それから、彼は、極度の疲労と睡魔のために鉛のように重い体を、ひとときの安息を与えてくれた小椅子から引っぺがし、やむなく立ち上がった。
アンドレスはコイユールの方に向くと、早口ながらも、噛み含めるように言う。
「俺は行かなきゃならないけど、また時々、顔を出すよ。
君のことが心配だし、アレッチェの容態も気になるからね。
だから、コイユール、決して一人で無茶してはいけないよ」
一方、コイユールは、寝台に横たわるアレッチェの方を気にかけながら、追い立てられるように出口に向かっていくアンドレスを追って立ち上がった。
彼女が横目でチラリとアレッチェに視線を走らせると、今は彼の両瞼はしっかり閉じられ、深い昏睡状態に陥っているように見える。
だが、ほんの少し前には、包帯の隙間から薄眼を開けて、隙無くこちらを観察しているように感じられてならなかった。
あれは目の錯覚だったのだろうか。

そのことを一言告げたくて、コイユールがアンドレスを追って扉に進みかける。
「あの、アンドレス」
しかし、衛兵たちが、野太く叫び合う大音声に、コイユールの遠慮がちな声はあっさり掻き消された。
「どうやらケンカは四階の軽症者の治療場のようです」
「スペイン兵とインカ兵が悶着を起こしているとの報告です」
「こんな夜中に騒ぎを起こして、他の負傷兵にとっちゃ、いい迷惑ですぜ。
そう思いませんか、アンドレス様」
口々に言う衛兵たちの言葉に、アンドレスも「ああ、今はケンカよりも静養が必要だ」と、限界を超えた疲労感を隠して頷いた。
ひどく疲労しているのは、自分だけではなく、この砦の誰もがそうなのだ。
(それにしても、スペイン兵とインカ兵を同室にしたツケが、早速、出てしまったな)
彼は胸中で密かに溜息をつき、アレッチェの居室を出かけて、もう一度、コイユールを振り向いた。
そして、「また来る!」と片手を上げて、笑顔を見せる。
(アンドレス!)
コイユールが言葉を呑んで立ち尽くしている間にも、当のアンドレスは、衛兵たちに急き立てれらてアレッチェの居室から飛び出して行った。
コイユールとアレッチェの二人きりに戻った室内を、冷え冷えとした静寂が再び支配する。
今しがたまでアンドレスの温かなぬくもりと共に居ただけに、彼が去った後の部屋は、ひどく隔絶された陰鬱な空間に感じられた。
薄闇の中で、コイユールは息を潜め、また寝台の方へ目を凝らした。
やはり、アレッチェは昏々と眠っているように見える。
(先ほど、こちらを見ていたように思えたのは、気のせいだったのだわ)
コイユールは小さく安堵の息をつき、足音をしのばせて小椅子へ戻ると、自然療法を再開しようと寝台の方へ右手を伸ばした。
その刹那、突如、寝台の方から、ヌッ、と伸びてきた包帯巻きの片腕が、彼女の細い右手首に掴みかかった。
(あっ…!)
コイユールが声にならぬ叫びを上げる。
かたやアレッチェは、カッ、と目をむいて、捉(とら)えた彼女の手を物珍しげに見やっている。
「不思議な手だ。
さっき、おまえが手を当てていた部分から、焼けるような痛みが薄れていくのを感じた」
大量の煙を吸い込んで喉もやられているらしく、アレッチェの声は擦れていたが、それでも地を這うような低音には不気味な凄味が宿っている。
驚愕と恐怖で、コイユールの心臓は口から飛び出しそうなほど激しく脈打ちだす。
それでも、彼女は、懸命に平静を装おうと努めた。
「いつから目を覚ましていらしたのですか」
「さあ?」
「眠った振りをして、私たちの会話を盗み聞きしていたのですか?」
沈着に応じようとしても、コイユールの押し殺した声には、どうしても不審の色が滲む。
「せっかくの恋人たちの逢瀬を邪魔立てしたくなかったのだ。
それにしても、あのトゥパク・アマルの秘蔵っ子のアンドレスが、おまえのような端女(はしため)と出来ていようとは。
このことをトゥパク・アマルは知っているのか?」
包帯の下で、クックッと、くぐもった笑い声を漏らし、毒を吐くように言うアレッチェに、コイユールは絶句したまま硬直している。
対するアレッチェは、掴んでいたコイユールの手首を無造作に投げ捨てると、いきなり体を起こしはじめた。
「まだ起きてはなりません」
コイユールが慌てて止めようとするが、その両手を乱暴に振り払ってアレッチェは上半身を起こし、寝台の背にもたれかかった。
と見るや、彼の左腕に巻きつけられた厚い包帯を、素早く右手で解きはじめる。
「おやめください。
まだ包帯を取っては駄目です」
懸命に止めようとするコイユールを、アレッチェは頭ごなしに怒鳴りつけた。
「黙れ!
自分の傷の具合を確認してはならぬ法がどこにある」
「ですが……」
彼女が半ば涙を滲ませた目でハラハラと見守る間にも、アレッチェは荒々しく自らの左腕の包帯を拭い去り、露わになった地肌を喰い入るように凝視している。

生々しく水ぶくれ、無残に焼け爛(ただ)れた肌に視線を落とすアレッチェの鋭利な目元は、ヒクヒクと引きつり、不規則に痙攣している。
アレッチェ自身が予想していた以上に、実際の己の全身状態が悲惨であることを察したのであろう。
愕然とした彼の表情から、明らかに強烈な衝撃に襲われていることが痛いほど伝わってきて、コイユールの胸は軋(きし)んだ。
「アレッチェ様…」
「わたしの体全体は、どこもこのような状態か?
顔も、両手足も、体中が全てこうなのか?」
これまで遠目からしか垣間見たことのなかった敵将だが、鉄面皮の冷酷無比な表情か、エゴイスティックで残虐な表情しか見たことがなかった。
その同じ人物が、隠そうにも隠しきれぬ落胆に満ちた苦渋の声で問う様子がどうにも居た堪れず、コイユールは救急箱から清潔な包帯を取り出し、急いでそれを相手の腕に巻きつけていく。
「体の部位によって、損傷の程度には違いがあります」
これ以上、相手を絶望させたくなくて、コイユールは懸命に言葉を絞り出した。
確かに、体の部位によって、重症度に差異があるのは本当だった。
しかしながら、全体的には、今、彼が目にしたような酷い状態の部分か、もっと酷い部分が殆どではあったのだが。
それでも、彼女は、アレッチェを力付けたいと願わずにはいられない。
「どうか希望を失わないでください。
従軍医も、アレッチェ様は強いお人だから、普通の人なら厳しい状態でも、あなた様ならきっと生き延びるお力を備えていらっしゃると申しておりました」
「話をすり替えるな。
わたしが懸念しているのは、命に別状があるかどうかではなく、この禍々(まがまが)しい火傷痕が完治するかどうかということだ。
もし治らぬというなら、このような化け物同然の姿で生き延びて何になる」
またも己に向かって怒声を張ったアレッチェではあったが、先刻のような断固とした気迫は薄れている。
それだけ彼が深い失意の底にあるのだと察せられて、コイユールは、痛々しさに胸が張り裂けそうだった。
新しい包帯を巻きつけた相手の左腕を無意識のうちに優しく両手で包んで、「きっと良くなりますから」と、コイユールは祈るように呟いていた。
その時、不意に、彼女の両手を、アレッチェの厳つい右手が、ガッチリと握り締めた。
びっくりしてコイユールが目を上げると、ミイラのごとき敵将の顔が、己のすぐ面前にあった。
反射的に大きく身を引いた彼女の顔を、包帯の隙間から光るアレッチェの炯々(けいけい)たる両眼が、貫くように見据えてくる。
「おまえのその手で、このわたしを元通りに治せるか?
いや、なんとしても戻してもらわねばならぬ。
今、おまえは、きっと良くなると明言したな?
なれば、この惨たらしい焼け爛れた皮膚を元通りに戻し、軍人として十全な機能を備えた肉体に回復させるのだ」

「ええ?!」
コイユールは仰天して、息を詰まらせた。
痛みを和らげるとか、安眠に誘うとか、そうしたことなら自分にできても、重度の損傷を被った身体や機能を元通りに回復させるなど土台無理なことである。
「私には、そのような…」
言いかけたコイユールの小声を遮って、包帯に巻かれながらも鋼のように強靭な指で彼女の両手を強く握り締めながら、アレッチェが断固たる口調で宣言する。
「インカの秘伝の技とやらで、おまえがわたしを完治させることができたなら、わたしもインカ族どもを今より認めてやってもよい。
褒美として、おまえの望みも叶えてやろう。
どのようなことでも申してみよ」
アレッチェとの対話が危険な方向に誘導されているのを直感的に感じて、コイユールの理性は、早くこの場から逃げ出さなければいけないと警笛を鳴らしている。
しかし、彼女は、震えながらも身動きすることができない。
「ど、どのようなことでも?」
「そう、どのようなことでも叶えよう」
「それでは、この戦さを止めて、インカの人々を自由にして、アレッチェ様たちはご自分の国に帰ってくださるのですか?」
「おかしなことを言う。
この戦さを始めたのは、トゥパク・アマルの方ではないか。
おまえたちが反旗を翻すのを止めて、トゥパク・アマルが我らの元に投降すれば、いつでも戦さは止む」
そう嘯(うそぶ)いて、アレッチェは包帯の下で口端を吊り上げ、苦笑する。
それから、皮相な眼差しに変わってコイユールを睥睨(へいげい)しつつ、語を継いだ。
「だが、今ここで、そのような議論が不毛なことは、わたしも承知している。
それがおまえの望みというなら、考えてやってもよい。
とはいえ、そういうことは、わたしの一存では決めかねるのだ。
最終的に、副王の裁定が必要だ。
なれど、わたしから副王に、上手く口添えすることならできよう」
「本当…ですか?」
蒼白になったり、頬を紅潮させたり、顔色を目まぐるしく変えながらも、己の方に身を乗り出している目前のインカ娘を、アレッチェの双眸が冷徹に見据えて頷く。
「本当だ」
「ですが――」
これまで、このアレッチェは、インカ軍やトゥパク・アマルに対して幾度も盟約を撤回し、裏切りや嘘を繰り返してきたことを目の当たりにし続けてきた。
そのような人物の言葉を、いかに駆け引きなどに疎(うと)いコイユールでも、さすがに簡単に鵜呑みにすることはできない。
トゥパク・アマルとの誓約さえ手の平を返したように易々と撤回し続けてきたこのアレッチェが、なんの権力も財も持たぬ己との約束など守るはずがないではないか。
そんな彼女の心を見透かすように、アレッチェが、包帯の下から、くぐもった声で囁きかける。
「わたしが、また二枚舌を使って、おまえを騙すと思っているのなら、今回ばかりは取り越し苦労だと言っておこう。
いかに莫大な富や強大な権力を持っていようが、このような姿となった今、それらの金や力に如何なる意味があろうぞ?
ましてや、今や、わたしは囚われの身。
元通りのわたしの人相や肉体に戻れるのならば、それ以上、何をも望む気はない。
これは、まぎれもない今のわたしの本心だ」
そう語るアレッチェの声音は、彼にしては信じがたいことだが、微かに震えてさえいる。
包帯の隙間から垣間見える彼の目の色は、必死の様相を帯び、縋(すが)るようにこちらを見つめている。
もし誰か第三者が部屋に入ってきて、このアレッチェの台詞や振る舞いを客観的に眺めたとしたら、いかにも嘘くさい猿芝居だと感じたかもしれない。
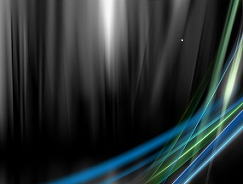
しかしながら、その場の空気に呑まれているコイユールにとっては、そんなアレッチェの表情が、包帯に隠されていながらも、ひどく切迫した苦悩に満ちたものに感じられてならず、彼が嘘を吐いているようには思えなくなっていた。
「慈悲深きインカの娘よ、どうかわたしを助けてくれ。
このような無残な姿のままなら、誠に如何なる所有物も力も全く無意味であり、もはや命を永らえたいとも思わぬ」
「そんな――人は、外見や、五体満足であることだけが、全てではありません」
アレッチェを力付けたい一心からではあったが、思わず反論してしまったコイユールを、険しさを増したアレッチェの両眼が突き刺すように睨(ね)めつける。
「口先だけの綺麗事など聞きたくもない」
「口先だけで申し上げているつもりはありません」
「ほう?
おまえは本心からそう思っていると?
ならば、もしわたしの治療に失敗した時には、おまえも火をかぶり、わたしと同じ姿になってみせよ」
「そ、そんな……!!」

あまりに極端に走ったアレッチェの要求に、激しく混乱し、驚愕して、切り返す言葉を失っているコイユールに、「驚くような条件ではあるまい」と、アレッチェが冷ややかに語を継いでいく。
「冷静になって考えてみよ。
これは、おまえにとって、なかなか良い取り引きだ。
おまえがわたしを完治させて治療に成功すれば、インカ側に有利となるよう、わたしは副王に和平の交渉を勧め、結果、おまえは救国の英雄になれるのだ。
それに対して、おまえが治療に失敗すれば、わたしには僅かな慰めが残るだけだ」
「僅かな慰め?」
「おまえが全身火傷のわたしと同じ悲惨な姿となれば、わたしは孤独な死路を共にする僕(しもべ)を得られる」
「し、しもべ?」
「そう、惨めさを分かち合う、おまえという僕だ。
だが、それだけのこと。
つまり、この取り引きは、圧倒的におまえに有利な条件ということだ。
おまえの戦利品は祖国に平和と主権と豊かさを取り戻すという壮大無辺なものであり、一方、おまえのリスクはおまえ個人に限られた極過小なもの。
絶対的におまえにとって好都合な条件であることは、誰の目から見ても明らかだ」
「そのような無茶なこと私には……」
「まさか、これほどの好条件を呑めないなどと言うまいな?
もし拒絶するというならば、所詮、おまえは、無数のインカの民の命よりも、自分のことの方が大事だということだ。
なぜなら、わたしの治療に成功すれば国家や民族を救うという献身的な偉業を成し遂げられる上、たとえ治療に失敗したとしても失うのはおまえ自身の身ひとつだけなのだから」
ぐっと言葉に詰まり、次第に思考が回らなくなって、表情も全身も強張らせているコイユールの両手を、アレッチェの包帯巻きの大きな右手がギュッと強く握り締める。
「わたしは本気で懇願している。
わたしを助けてくれ。
もちろん、おまえ一人の力だけでなく、従軍医たちと協力してもらって構わない。
わたしも、おまえの良き患者となると誓おう。
故に、おまえもわたしとの約束を守り、命を賭けて最善を尽くすと誓ってくれ」

アレッチェに強烈な言葉を弾丸のように次々と撃ち込まれ、コイユールの思考は停止し、真っ白な状態に陥っていた。
それでも、アレッチェのいかにも傲慢に聞こえる一言一言の裏に、彼の真に必死の思いが少なからず宿っていることを、コイユールは生々しく感じ取ってもいた。
プライドの極度に高いアレッチェにとっては、彼の言葉通り、焼け爛れた全身を隠し人目を避けて不本意な生涯を送るぐらいなら、莫大な富も強大な権力も捨てて死んだ方がマシだというのは、百パーセントではないにしろ、少なからず彼の本音であろうと思われた。
生命に対する何という不遜であろうかと苦々しく感じる一方で、いかにも人間臭いアレッチェの苦悩が全く理解できぬわけでもなかった。
ますます混迷を深めていく彼女の思考の中で、アレッチェの持ち出した取り引きが、上手くいけばインカ全体のために役立つ可能性がある一方、上手くいかなくても自分が責を負うだけで済むものであることも、彼の言葉通りであると思えてくる。
そしてまた、今回ばかりは虚偽の約束ではないと強く主張するアレッチェの言葉を受け入れることが、困難な治療に共に立ち向かうために必要な信頼関係を構築するための重要な第一歩になるのではないか、とも直感的に感じていた。
「――わかりました」
コイユールは、半ば虚(うつ)ろな、それでいて、覚悟と決意を宿した目で、真っ直ぐアレッチェを見上げた。
「アレッチェ様がそこまで仰ってくださるのであれば、お申し出を承りましょう。
貴方様のお言葉を信じ、私の全身全霊を尽くすと誓います」
その言葉にアレッチェも満足気に顎を引いて、微かな笑みをたたえながら、家臣に応ずるように厳然と応える。
「さすがインカの誇り高き娘、よくぞ申した。
では、これで、わたしとおまえの盟約は交わされた」
血の気を失った唇をギュッと噛み締め、俯(うつむ)き加減に頷くコイユールに、包帯の奥から覗くアレッチェの視線が執拗に絡みつく。
「おまえの名は?」
「コイユール」
「では、コイユール、念のため言っておくが、この賭けは、わたしとおまえだけの秘密だ。
トゥパク・アマルにも、アンドレスにも、誰にも口外することは許さぬ。
あの者たちが知れば、いらぬ横槍を入れてきて、せっかくの我々のゆるぎなき神聖なる決意が台無しにされよう。
よいな?」
「分かっております」
コイユールは、今にも涙の零れそうな黒曜石の瞳を揺らしながら、力無く頷いた。
彼女自身、このような無謀な約束をアレッチェとしてしまったことなど、決して誰にも言うことなどできないと感じていた。
特に、アンドレスが知ろうものなら、どれほど大きな心配をかけることだろうか。
それに、自分がこのような勝手な約束をしてしまったことで、かえってトゥパク・アマルやインカ軍に多大な迷惑をかける事態になりはしないだろうか?
抑えようにも彼女の全身はカタカタと目に見えるほどに震え、いよいよ早鐘のごとく心臓は脈打っていたが、もはや全力を尽くすのみである。

ジジジ…と低い音を立て、部屋の四隅に置かれた燭台の一つが、蝋を失い、フッ、と消える。
深い地底のように静まり返った室内は、濃さを増した闇と凍えそうな冷気に、重く押し呑まれていった。
回廊を慌ただしく進みながら、アンドレスがチラリと目をやった覗き窓からは、夜明け前の澄んだ藍色の空が垣間見える。
いつしか、すっかり嵐も去った天空には、美しい月さえも輝いている。

しかし、そのような清浄な光景に一時も目を留める間もなく、インカ兵に引っ張られるようにして彼がケンカの現場に着くと、そこは砦の四階部分に設けられた比較的軽傷者たちが収容されている治療場であった。
砦内にある寝台の殆どは重症者の治療場に移動されていたため、この治療場の負傷兵たちは床の上に横たえられている。
とはいえ、石床の冷たさで体が冷えぬよう、厚く筵(むしろ)を重ねた上にシーツが敷かれており、室温も適度に保たれているため、何事も無ければ、安眠するのに十分であろうと思われた。
現に、今も、殆どの負傷兵たちは部屋の一隅で起きている喧騒を無視して、「うるせぇなあ…」と眉をひそめながらも、毛布にくるまったまま起き出そうとはしなかった。
重症者同様に軽傷者の治療場も幾つかの部屋に分かれており、アンドレスが訪れたその室内には、40〜50人ほどが収容されていると見受けられた。
彼が目を凝らすと、部屋の奥まった一角に、薄暗がりの中にもかかわらず、十数名と思しき人だかりのシルエットが黒々と浮かび上がって見えてくる。
そして、そちらの方角から、ケチュア語とスペイン語の入り乱れた罵声や怒鳴り声が響いてくる。
(あれか!)
アンドレスは、足元に横たわっている多数の負傷兵を踏みつけないよう気を付けつつも、小走りで人だかりの方に向かう。
「おまえたち、今、何時だと思ってるんだ?
そんな大声を出したら、他の者たちが眠れないじゃないか」
騒ぎに群がっているインカ兵やスペイン兵の人垣を掻き分けながら、アンドレスがケンカの当人たちに向かって、厳しい口調で言う。
すると、ケンカの当事者と思しき二人の兵が、バッと、アンドレスを振り向き、「だけど、こいつがっ!!」と、同時にさらに声を張り上げた。
一人はインカ兵、もう一人はスペイン兵で、両者共に20台後半から30台前半位と見て取れる。
「アンドレス様、このスペイン兵が俺の大事な手紙を踏みつけにしやがったんです!」
「おまえが勝手に床に紙をバラまいていたんじゃないか!
そのせいで、俺は暗い中で足を滑らせて、怪我を悪化させちまったんだぞ」
(こりゃあ、何やら、それぞれに言い分がありそうだ)
まだ状況がサッパリ掴めずにいたが、それでも、アンドレスは心の内でそう呟いた。
アンドレスは、今にも殴り合いに発展しそうな二人の間に割って入る。
そして、「二人共、少し落ち着いてくれ」と、自らも平静を保とうと深く息を吸い込んだ。
「二人でいっぺんに話されたら、何が何だか分からない。
ちゃんと双方の話を聞くから、順番に話してくれないか」
すると、クシャクシャになった紙のようなものを握り締めたインカ兵が、それをアンドレスの方に差し出しながら、すかさず口火を切った。
「アンドレス様、見てください!
これ、倅(せがれ)から送られてきた手紙なんです。
それを、このスペイン兵が、泥だらけの汚ねえ足で踏みつけにしやがったんです」
強度の悔しさと悲しさが混じりあった表情で切歯扼腕しているインカ兵から、アンドレスは、その手紙の束らしきものを受け取った。
確かに、その中の数枚が無残なほどシワだらけになっている。
その上、シワクチャの紙面には、大きな軍靴の足跡がドッカとついて、もはや文字が判別できるような状態ではなかった。
さすがに気の毒になって、なんとかシワを伸ばせないかと紙を引っ張りながら、アンドレスが優しく問う。
「君の所属と名前は?
君の息子さんが送ってきた手紙なのか?」
「はい」

怒りに燃えていた瞳の奥に、今は深い郷愁の色を宿して、インカ兵が溜息混じりに答える。
「俺は、ビルカパサ様の連隊に入っている歩兵のペドロと申します」
「何か大事なことが書かれていた手紙なのか?」
「いえ、内容は日常の様子を綴ってある他愛ないものです。
ですけど、故郷の家に残してきた9歳になる倅が、何年も帰還していないわたしを恋しがって、懸命にスペイン語の文字を覚えて、書き送ってくれたものなんです」
「そうだったのか…」
アンドレスは、ペドロと名乗ったインカ兵の言葉を聞きながら、胸痛む思いで自分の手の中の手紙に目を落とした。
インカには文字が無いため、手紙を書くにはスペイン語をマスターするしかない。
とはいえ、この時代、殆どのインカの人々は貧しく、まともに学校にも行けていないため、スペイン語の筆記を覚えようとしても容易なことではなかった。
軍靴の大きな足跡が泥の判をついたようにベッタリこびり付いたグシャグシャの紙片上で、ところどころ判別できる文字は、決して上手とは言えないが、子供らしい元気いっぱいな、そして、一生懸命な字体である。
もう何年も帰宅できていない父親に、子供たちはどんなに会いたがっていることだろう。
いや、子どもたちだけでなく、奥さんや両親など、残された家族誰もが、戦地に赴いた父親の無事を祈りながら再会の時を切望しているに違いない。
それもこれも、インカ軍幹部の自分たちが、この反乱を長引かせてしまっているためなのだと、アンドレスの胸はいっそう強く痛んだ。
周りでケンカの野次馬をしていた他の兵たちも、インカ兵やスペイン兵の別を問わず、皆、郷里や国に残してきた家族を思い出しているようで、いつしかシンミリした雰囲気が辺りを包んでいる。

しかし、その空気に負けじと、ケンカのもう一方の当事者であるスペイン兵が、いよいよ憤然と鼻息を荒げてペドロを睨み、吐き捨てるようにがなった。
「おまえ、人聞きの悪い言い方をするんじゃねえぞ!
俺は、わざとその手紙とやらを踏んだわけじゃない。
床の上に、もともと落ちていたんだ。
部屋は薄暗いし、足元なんか、まともに見えない。
おかげで、洗面所から戻ってきた俺は、その紙を踏んじまって、足を滑らせ、尾てい骨を強く打って、せっかく腰の傷が少し良くなっていたのに台無しだ!」
「なんだとぉ?!
人の大事な手紙を踏みつけておいて、その言い草は無いだろう!!」
二人がまた怒鳴り合い出したのを、「待て、おい!」と止めようとするアンドレスの肩を、傍で見守っていた別のインカ兵が軽く叩いた。
「君は?」
「俺は、ペドロの同輩です。
ペドロの言っていることも本当ですし、あのスペイン兵の言っていることも本当なんです。
ペドロのやつ、あの手紙を前のベースキャンプにいた時に受け取ったんですが、それ以来、すごく大事にしていて、寝る前に、毎晩、必ず読み返すんです。
それで、読みながら眠っちまうことが多くて、そうすると手元から床に落としちまうこともしょっちゅうで」
「そうだったのか。
教えてくれて、ありがとう」
アンドレスは、ペドロの友人の肩を軽く叩き返して礼を伝えると、いよいよ殴り合わんばかりに激しくやり合っている二人の間に割って入り、どうにかして止めようとする。
「ペドロ、君の気持ちもよく分かるが、彼がわざと踏んだってわけじゃないことも本当なんだ。
ここは俺に免じて、なんとか気持ちを抑えてくれないか」
アンドレスの懸命な言葉に、「ですが…」と、ペドロが少し大人しくなるも、この時とばかりに相手のスペイン兵が大きく身を乗り出し、ペドロに向かって怒鳴りつける。
「それみろ、俺の言った通りじゃないか。
そもそも被害に合ったのは、こっちの方だ。
戦場でもないどころか、治療場の中で、怪我を悪化させる羽目になった責をどう取るつもりだ」
その時、ケンカの人だかりの背後に、ヌッと、巨体の大男のシルエットが現れ、と見るや、雷(いかづち)のごとく野太い大音声が、全ての喧騒を貫いて轟然と響いた。
「いい加減にせんか!!」
ケンカの当事者はもちろん、その場にいた誰もが、ギョッ、として身を縮め、声の主を振り返る。
そこには、厳しい表情をした壮年のスペイン兵が、松葉杖を片手に仁王立ちになり、こちらに鋭い睨みを利かせていた。
立派な顎髭をたくわえ、足の負傷にもかかわらず頑強そうな体躯は貫禄たっぷりで、軍服の分厚い胸には多数の勲章が並んでいる。
アンドレスにとっては初めて見る人物であったが、その装束や強烈な存在感から、スペイン軍の高位の将官であろうことは、すぐに察しがついた。
事実、先ほどまで大上段に構えて怒鳴りまくっていたペドロのケンカ相手のスペイン兵は、急に大人しくなって、今はペドロの陰に隠れんばかりである。
そのスペイン軍将官と思しき人物は、ペドロの陰で体を小さくしているスペイン兵を険しく一瞥(いちべつ)すると、断固とした口調で言明する。
「どっちもどっちだ。
これ以上、騒ぎを続けて、皆の睡眠妨害を継続することは許さん。
ヨハン、分かったか?
分かったら、もう黙って寝所に戻りたまえ」
ヨハンと呼ばれたペドロのケンカ相手は、「はっ…、カザルス様…!」と大いに畏まって、ますます身を屈(こご)めながら後ずさっていく。
アンドレスは、場を収めてくれたスペイン将兵に心から礼を述べた。
「お騒がせして申し訳ありませんでした。
そして、お力を貸して頂けたことに感謝します」
それから、アンドレスは、ペドロとヨハンの方にも改めて向き直る。
「ヨハン殿、そして、ペドロ、二人共、まだいろいろ思うところはあるだろうけれど、どちらも悪気があった訳ではないことだから、どうか今回は互いに堪忍してほしい。
ペドロ、君の息子さんのことを聞かせてもらえて、とても嬉しかった。
それから、ヨハン殿の怪我の悪化については、申し訳なく思っている。
俺から従軍医に頼んで、朝一番に診てもらえるように手配しておくから、この場はこれで」
そう二人に告げて、今度は周りに集まっていた者たちの方に目をやるも、カザルスの出現に気圧されたのか、いつしか野次馬連中たちはそそくさと自分の寝床に引き返しており、室内にはやっと静けさが舞い戻っていた。
カザルスが厳しい眼を光らせているために、ヨハンもササッと毛布の奥深くまでもぐりこんで、ケンカ相手を失ったペドロも傷(いた)んだ手紙を大事そうに抱いたまま横になった。
室内が落ち着いた様子を見届けると、アンドレスは改めてカザルスに礼を払い、彼を伴って回廊へ出た。
夜明け近い回廊には、薄っすらと朝の気配が漂い、窓からは潮騒と共に清々しい爽風が流れ込んでいる。

「この度は、お力をお貸しくださり、どうもありがとうございました。
わたしは、トゥパク・アマル軍の――」
アンドレスが畏(かしこ)まった挨拶を述べている間にも、カザルスは、松葉杖を片手に窓際で大きく深呼吸をして、それから、こちらに改めて視線を戻した。
「アンドレス殿ですな。
若くしてインカ軍の副指揮官、剣の達人と、噂はかねがね聞いています。
わたしは、スペイン軍総指揮官ホセ・アントニオ・アレッチェ直属の陸軍歩兵大将カザルスです。
以後、お見知り置きを」
熟練の軍人らしい貫禄と沈着さを兼ね備えたカザルスの風貌を見つめながら、アンドレスは言葉にならぬ深い感慨を覚えていた。
「カザルス殿、お目にかかれて光栄です」
「わたしも同じ気持ちですぞ、アンドレス殿。
貴殿方々は、豪雨で血と泥の海と化した戦場に、敵兵である我ら負傷兵を捨て置くことなく、砦に一兵一兵運び入れ、丁寧な治療を施している。
貴殿達インカ軍には、我らが失いかけている騎士道精神があるように思う」
「いえ、元々は、ここはスペイン軍の砦ですし、食糧や医薬品もここに保管されていたものを多く使わせて頂いています。
それに、敵味方の別無く、負傷兵を助けるのは、古(いにしえ)のインカ時代からの伝統なのです。
我らの総指揮官トゥパク・アマルが、そういう人物でもありますし」
トゥパク・アマルの名を聞いて、カザルスの強い光を宿した双眸が遠くを見る眼差しに変わる。
「トゥパク・アマル殿と、直接、相見(あいまみ)えたのは、わたしは此度の戦場が初めてであった。
昨日の戦闘で、彼が率いる騎兵部隊による抜剣攻撃を受けたが、あれは想像を絶する壮烈さであった。
あの者たちの命知らずな突撃は電光石火で、あの時、我らは迎え撃つための戦闘隊形を整えることさえできなかった。
トゥパク・アマル殿の騎馬隊は動きを捕捉できぬほど敏速であった上、我らの銃を微塵も臆せず、猛然と突撃敢行してきたのだ。

その挙句、我らは大量の銃を携えていたにもかかわらず、たちまち蹴散らされた。
あの瞬間、あの者たちには、まるで鬼神が乗り移っているかのようであった」
昨日の戦場に舞い戻ってしまったかのような相貌になり、太い声で噛み締めるように語るカザルスの言葉に、アンドレスもまた強く惹きつけられて聞き入っていた。
これまでの戦いで、作戦上、トゥパク・アマルの部隊と別行動になることの多かったアンドレスにとって、トゥパク・アマルの実際の戦いぶりを知る機会は限られていたからだった。
⇒ 連載中のブログへ (当HPより一足速く更新しております)
【登場人物のご紹介】 ☆その他の登場人物はこちらです☆
≪トゥパク・アマル≫(インカ軍)
反乱の中心に立つ、インカ軍(反乱軍)の総指揮官。
インカ皇帝末裔であり、植民地下にありながらも、民からは「インカ(皇帝)」と称され、敬愛される。
インカ帝国征服直後に、スペイン王により処刑されたインカ皇帝フェリペ・トゥパク・アマル(トゥパク・アマル1世)から数えて6代目にあたる、インカ皇帝の直系の子孫。
「トゥパク・アマル」とは、インカのケチュア語で「(高貴なる)炎の竜」の意味。
清廉高潔な人物。漆黒長髪の精悍な美男子(史実どおり)。
≪アンドレス≫(インカ軍)
トゥパク・アマルの甥で、インカ皇族の青年。
剣術の達人であり、若くしてインカ軍を統率する立場にある。
スペイン人神父の父とインカ皇族の母との間に生まれた。混血の美青年(史実どおり)。
ラ・プラタ副王領への遠征から帰還し、現在は、英国艦隊及びスペイン軍との決戦において、沿岸に布陣するトゥパク・アマルのインカ軍主力部隊にて副指揮官を務める。
≪ロレンソ≫(インカ軍)
アンドレスが学生時代を過ごしたクスコ神学校時代の朋友。生粋のインカ族。
反乱幕開けと共に、インカ軍に参戦した。
アンドレスに比して大人びた風貌と冷静な性格を有し、公私に渡ってアンドレスを助けてきた。
トゥパク・アマルからの信頼も厚く、アンドレスと共にインカ軍本隊の若武者たちを統率している。
トゥパク・アマルの妻であり同志。トゥパクとの間に生まれた3人の皇子たちの心優しき母でもある。
褐色の女神のように麗しくも、戦士のごとく雄々しきインカ族の才媛。
現在は、サンガララの本陣を守りながら、国中に戦線拡大しているインカ軍全軍の補給などを取り仕切っている。
≪コイユール≫(インカ軍)
インカ族の貧しくも清らかな農民の少女。義勇兵として参戦。
代々一族に伝わる神秘的な自然療法を行い、その療法をきっかけにアンドレスと知り合う。
アンドレスとは幼馴染みのような間柄だったが、やがて身分や立場を超えて愛し合うようになる。
『コイユール』とは、インカのケチュア語で『星』の意味。
≪マルセラ≫(インカ軍)
トゥパク・アマルの最も傍近い護衛官である重臣ビルカパサの姪。
アンドレスやロレンソと同年代の年若い女性だが、青年のように闊達で勇敢な武人。
女性ながらもインカ軍をまとめる連隊長の一人。
≪ビルカパサ≫(インカ軍)
インカ族の貴族であり、トゥパク・アマル腹心の家臣。
トゥパク・アマルの最も傍近い護衛官として常にトゥパク・アマルと共にあり、幾度と無く命を張って主を守ってきた。
「ラ・プラタ副王領」の豪族で、トゥパクの最も有力な同盟者。
「猛将」と謳われる一方で、破天荒で放蕩な性格の持ち主だが、実は、洞察と眼力が鋭く、全体をよく見通している。
かつてアンドレスを戦士として鍛え上げた恩師でもある。
≪従軍医≫(インカ軍)
トゥパク・アマル軍に属する従軍医の一人。
高齢だが経験豊富で腕が良く、かつてトゥパク・アマルが戦場で重症を負った際も回復させた。
≪ディエゴ≫(インカ軍)
インカ皇族で、名実共にトゥパク・アマルの右腕的存在。
トゥパク・アマルの亡き父親ミゲルの弟の長男(トゥパク・アマルの従弟)。
勇猛果敢な武人で、アンドレスの叔父でもある。
現在は、トゥパク・アマル軍を離れ、聖都奪還のためにクスコで戦っている。
≪ジェロニモ≫(インカ軍)
義勇兵としてインカ軍に参戦する黒人青年。
スペイン人のもとから脱走してインカ軍に加わった。
此度の作戦では、アンドレス隊に属する多くの黒人兵を統率し、アンドレスを補佐している。
≪ホセ・アントニオ・アレッチェ≫(スペイン軍)
植民地ペルーの行政を監督するためにスペインから派遣されたエリート高官(全権植民地巡察官)で、植民地支配における多大な権力を有する。
ペルー副王領の反乱軍討伐隊(スペイン王党軍)総指揮官として、反乱鎮圧の総責任者をつとめる。
有能だが、プライドが高く、偏見の強い冷酷無比な人物。
名実共に、トゥパク・アマルの宿敵である。
スペインの植民地であるペルー副王領を統治する副王ハウレギの息子。
反乱鎮圧に手こずる軍に痺れを切らした副王による派兵されたスペイン王党軍を統率している。
≪エドガルド≫(スペイン軍)
副王の嫡男アラゴンへの絶対的忠誠を誓う腹心の部下。
スペイン王党軍を統率するアラゴン王子の副官でもある。
≪ドロテオ≫(スペイン軍)
スペイン軍総指揮官ホセ・アントニオ・アレッチェの親衛部隊長。
危機に瀕したアラゴン王子を救出すべく、インカ兵に扮してアラゴンやエドガルドの元に馳せ参じた。
≪サルセード大佐≫(スペイン軍)
此度の沿岸部におけるインカ軍及び英国艦隊との決戦において、砦のスペイン軍を束ねている。
当地での戦いにおいて、スペイン軍総指揮官アレッチェの補佐官の任にある。
≪カザルス≫(スペイン軍)
スペイン軍総指揮官ホセ・アントニオ・アレッチェ直属の陸軍歩兵大将。
沿岸部におけるトゥパク・アマルとの戦いにおいて、スペイン側の歩兵・騎兵・砲兵3000の混成部隊を統率・指揮している。
≪サウリ≫(スペイン軍)
沿岸部におけるトゥパク・アマルとの戦いにおいて、アレッチェ直属の陸軍歩兵大将カザルスの副官を務める。
≪ジョンストン提督≫(英国軍)
此度のペルー戦への進軍を行う英国艦隊の総指揮官。
英国王室の命により、トゥパク・アマルの反乱に乗じて、敵対するスペインを撃退し、当地を英国の植民地にしようと狙い定めている。
植民地生まれの白人(クリオーリョ)の革命分子を束ねるリーダー。
ただし、一般的に貧しいクリオーリョたちとは異なり、当地生まれでありながらも富裕層に属するらしきスペイン人。
トゥパク・アマルの反乱に乗じて、スペイン本国による植民地支配を瓦解させる機会を狙っている。
⇒ 連載中のブログへ (当HPより一足速く更新しております)
![]() (1日1回有効)
(1日1回有効) ![]() (随時)
(随時)
ランキングに参加しております。お気に入り頂けましたら、クリックして頂けますと大変励みになります!どうもありがとうございます。